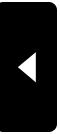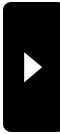2012年01月13日
対馬紀行-石垣のまち 22
つづき
厳原は古代には国府、中世から近世にかけては対馬藩主である宗家の居館がおかれ、対馬の政治・経済・文化の中心として栄えた城下町だった。今でも街なかに、背丈より高い石垣(石塀)が多く残っている。軒下ほどもある高さは、かつて訪れた朝鮮からの使節に武家の生活をのぞかれないようにするためだったと一説では言われてるそうだ。



特に、現在の厳原港から厳原町中村・宮谷・桟原地区へと続く大通り(現在の国道382号)は 「馬場筋通り」 と呼ばれ、両側に宗家一門及び家中上士の屋敷が門を並べていたそう。今でもこのあたりは武家屋敷町と呼ばれ、立派な屋敷跡が残っているそうだ。
また厳原の街なかには、一般的な石垣塀とは違った高さ3m、巾1.5mの高い石垣がある。この石垣は火災の類焼を防止するために設けられたもので 「火切」 と呼ばれる。府中の町は記録的な大火を何度も経験したことから、昔の町割りの線に沿って設けられたのだそう。現在残っているのは数か所だけだが、火に焙られた黒い痕跡のある石も見られ、石垣には築造年月等が刻まれているそうだ。
この辺りには史跡や文化財などの見どころがたくさんあるようだ。是非またゆっくりと時間をかけて散策してみたい。
つづく
厳原は古代には国府、中世から近世にかけては対馬藩主である宗家の居館がおかれ、対馬の政治・経済・文化の中心として栄えた城下町だった。今でも街なかに、背丈より高い石垣(石塀)が多く残っている。軒下ほどもある高さは、かつて訪れた朝鮮からの使節に武家の生活をのぞかれないようにするためだったと一説では言われてるそうだ。
特に、現在の厳原港から厳原町中村・宮谷・桟原地区へと続く大通り(現在の国道382号)は 「馬場筋通り」 と呼ばれ、両側に宗家一門及び家中上士の屋敷が門を並べていたそう。今でもこのあたりは武家屋敷町と呼ばれ、立派な屋敷跡が残っているそうだ。
また厳原の街なかには、一般的な石垣塀とは違った高さ3m、巾1.5mの高い石垣がある。この石垣は火災の類焼を防止するために設けられたもので 「火切」 と呼ばれる。府中の町は記録的な大火を何度も経験したことから、昔の町割りの線に沿って設けられたのだそう。現在残っているのは数か所だけだが、火に焙られた黒い痕跡のある石も見られ、石垣には築造年月等が刻まれているそうだ。
この辺りには史跡や文化財などの見どころがたくさんあるようだ。是非またゆっくりと時間をかけて散策してみたい。
つづく
Posted by dilbelau at 15:30│Comments(0)
│日本