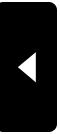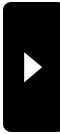2009年05月26日
'09.5.26(火)なぜ「七」光りなのか??
毎週月曜日に開かれている、鄭戊錬先生の勉強会。
日本語を勉強している韓国人が20人弱集まり、日本語で書かれた小説などを読みながら日本語の勉強をするもの。
現在読んでいるのは、木村治美さんの 『心をこめて家族の時間』 というエッセイ。
その中に 「親の七光りを期待できるひとのみに…」 というくだりがあった。
鄭先生が、親の七光りというのはどういう意味か説明され、皆さん納得されたかのようだったが、ふとある方が、
「先生、親の七光りの意味は分かりましたが、じゃあどうして 「七」 光りなんですか?」
これには一同首をかしげる。
私も首をかしげる。今までそんなこと、考えてみたこともなかった。
鄭先生がその語源を調べてくださっている間、参加者たちは
「親が100%だとしたら子供は70%程度だってことじゃないの?」
「仏像の後光の数と関係あるんじゃない?」
「虹も七色だから、それと何か関係があるとか?」
「でも虹の色の数って世界共通じゃないんだってよ。え?日本も7色?韓国と同じね。でもアメリカじゃあ6色なんだって。」
「へぇ~、何色が抜けてるの?」
「藍色だって」
など、銘々いろいろな推理をしている。
しかし、結局その場でははっきり分からなかったので、帰宅後調べてみると、
『三省堂「大辞林第二版」によりますと「七は大きな数として使う」と出ています。
要するに「大きな・偉大な」という意味で使われただけで、七つ何か意味があるというのではないようです。』
とのこと。
なるほど~。
さらにもう一つ。
同じエッセイの中の、今度は 「何の先生になるかは二の次で、…」 というくだり。
先ほどの 「七光り」 の質問の方とは違う方が、
「先生、『二の次』 が 『二番目、後回し』 だという意味なのは分かりましたが、例えばこの 『二』 を他の数字に変えて使うことはできますか? 『一の次』 とか 『三の次』 とか…」
これはNOだということは私にも分かる。
だが、なぜ 『二』 の次なのか。ついでに調べてみると、
『三省堂「新明解国語辞典」によると、この場合の「の」は同格を示す』
のだそうだ。
例えば、「昼食の(=である)カレーライス」、「部下の(=である)佐藤さん」 などのように、「二の次」 は 「2(番目)である次」=つまり 「2番目」 ということらしい。
なるほど。
これらの言葉を何の疑問も感じずに使っていた 日本語母語話者である私には、思いもつかなかった新鮮な疑問。
鄭先生が常々おっしゃる 「人間、死ぬまで勉強ですよ」 というお言葉が頭をよぎった。

日本語を勉強している韓国人が20人弱集まり、日本語で書かれた小説などを読みながら日本語の勉強をするもの。
現在読んでいるのは、木村治美さんの 『心をこめて家族の時間』 というエッセイ。
その中に 「親の七光りを期待できるひとのみに…」 というくだりがあった。
鄭先生が、親の七光りというのはどういう意味か説明され、皆さん納得されたかのようだったが、ふとある方が、
「先生、親の七光りの意味は分かりましたが、じゃあどうして 「七」 光りなんですか?」
これには一同首をかしげる。
私も首をかしげる。今までそんなこと、考えてみたこともなかった。
鄭先生がその語源を調べてくださっている間、参加者たちは
「親が100%だとしたら子供は70%程度だってことじゃないの?」
「仏像の後光の数と関係あるんじゃない?」
「虹も七色だから、それと何か関係があるとか?」
「でも虹の色の数って世界共通じゃないんだってよ。え?日本も7色?韓国と同じね。でもアメリカじゃあ6色なんだって。」
「へぇ~、何色が抜けてるの?」
「藍色だって」
など、銘々いろいろな推理をしている。
しかし、結局その場でははっきり分からなかったので、帰宅後調べてみると、
『三省堂「大辞林第二版」によりますと「七は大きな数として使う」と出ています。
要するに「大きな・偉大な」という意味で使われただけで、七つ何か意味があるというのではないようです。』
とのこと。
なるほど~。
さらにもう一つ。
同じエッセイの中の、今度は 「何の先生になるかは二の次で、…」 というくだり。
先ほどの 「七光り」 の質問の方とは違う方が、
「先生、『二の次』 が 『二番目、後回し』 だという意味なのは分かりましたが、例えばこの 『二』 を他の数字に変えて使うことはできますか? 『一の次』 とか 『三の次』 とか…」
これはNOだということは私にも分かる。
だが、なぜ 『二』 の次なのか。ついでに調べてみると、
『三省堂「新明解国語辞典」によると、この場合の「の」は同格を示す』
のだそうだ。
例えば、「昼食の(=である)カレーライス」、「部下の(=である)佐藤さん」 などのように、「二の次」 は 「2(番目)である次」=つまり 「2番目」 ということらしい。
なるほど。
これらの言葉を何の疑問も感じずに使っていた 日本語母語話者である私には、思いもつかなかった新鮮な疑問。
鄭先生が常々おっしゃる 「人間、死ぬまで勉強ですよ」 というお言葉が頭をよぎった。
鄭戊錬先生のご自宅にある돌하루방(トルハルバン)。
Posted by dilbelau at 17:23│Comments(2)
│学校・勉強会・試験
この記事へのコメント
・・・・・たしかに・・・・「七光り」も「二の次」も、なんにも考えずに使っていました・・。
なんだかものすごく目が覚めたような気分にさえ・・・。
なんだかものすごく目が覚めたような気分にさえ・・・。
Posted by とーと at 2009年05月26日 21:09
とーと さま
日本人でもそういうことに疑問を持つ人はいるんでしょうが、外国人ならではの新鮮な視線だと思いました。
それにしても、参加者の皆さん、本当に熱心に勉強されるんですよ。
いい刺激になります。
日本人でもそういうことに疑問を持つ人はいるんでしょうが、外国人ならではの新鮮な視線だと思いました。
それにしても、参加者の皆さん、本当に熱心に勉強されるんですよ。
いい刺激になります。
Posted by dilbelau at 2009年05月26日 22:24
at 2009年05月26日 22:24
 at 2009年05月26日 22:24
at 2009年05月26日 22:24