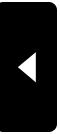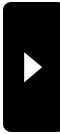2009年05月26日
'09.5.25(月)女子大生たちにモテモテ 銀瓶さん
つづき
落語を始める前に、まずは韓国語で自己紹介。韓国人の祖父母と両親を持つ在日3世であること、師匠は笑福亭鶴瓶さんであること、東京には500人、大阪には200人の落語家がいるが、韓国語で落語をするのは日本で自分1人だけだということなどなど。
また、偶然にも今日5月25日は、落語家である彼にとって大切な記念日。
今から21年前の1988年5月25日、師匠である鶴瓶さんから 「銀瓶」 という名前をつけてもらった日なのだそうだ。
そんな記念日に、ご自身の祖国である韓国で落語の公演ができるのは、とても感慨深いことだろう。
さて、自己紹介のあとは、小咄をいくつか披露。
そしていよいよ、韓国語の落語。
落語というものは、話す内容を頭の中で想像しながら聴いてください、想像しながら仕草を見てください、とあらかじめ観客に伝える。
韓国語の落語、題目は 「개 눈(犬の目)」。
とても表情豊かに、また滑らかな韓国語で話される落語に、観客は自然と引き込まれ会場は笑いの渦。
昨年も感じたが、一体どれほどの努力と練習を積み重ねたのだろうかと心を打たれる。
昨年は、韓国語の落語を2本披露されたが、今年は韓国語の 「개 눈(犬の目)」 の次は、日本語で 「手水回し」 を披露された。「手水(ちょうず)」 のことを 「長・頭(ちょうず)=長い頭」 のことだと誤解したことによる大騒動。あらかじめ理解しておかないと意味が分からないキーワードを説明され、それをふまえた上で聴いてください、という配慮もされていた。
これまた大爆笑。
実に楽しい落語で、大いに笑わせてもらった。
韓国人にとっては、もちろん韓国語で話した 「개 눈(犬の目)」 の方が理解しやすかったはずだが、むしろ 「手水回し」 の方が客席の笑いは大きかったように感じた。
それだけ、言葉の壁を越えて伝わるものがあったということだろうか。
また余興として、会場となった釜慶大学の日本語学部の学生数人を舞台に上げ、落語を体験してもらうという場面もあった。彼ら学生は、落語を通して日本語を勉強するという授業も受けているのだそうだ。

1人ずつ舞台に上がった日本語学部の学生と、日本語で話しながら 「扇子を使ってうどんを食べる仕草」 や 「扇子を使ってタバコを吸っている仕草」 などを指導し、体験してもらうというもの。
こんなふうに楽しく過ごした時間も、いよいよ最後の挨拶となった。
自分には祖父母や両親と同じように、韓国人の血が流れている。韓国のことを祖国だと感じたくて韓国語を習い始め、韓国の人にも日本の伝統芸能を伝えたくて韓国語で落語をするようになった。
皆さんが韓国で日本に興味を持って日本語を勉強されているように、日本にも韓国に興味を持って韓国について勉強している人がたくさんいる。
このように、2つの国の人同士が、それぞれお互いに興味を持ち、お互いのことを知るという交流は本当に大切なことだと思う。また、韓国に落語をしに来ます。
会場は再び大きな拍手と歓声。
銀瓶さんが舞台から下りて、会場の出入り口へ歩いていこうとすると、あっという間に学生たち(特に女子学生)に取り囲まれ、写真攻撃を受けていた。
とても気さくな銀瓶さん、携帯のカメラを向ける女子大生たちに向かって、立ち止まって顔を彼女たちの方に突き出し、カメラポーズをするという場面も。

完全に四方を学生たちに”包囲”されてしまった銀瓶さん。

至近距離で携帯カメラのレンズを向ける女子学生たち。私も記念に1枚と思ったが、とてもとても正面からは近づける状態ではなかった。

この後も、会場を出たあたりでは長い間、記念写真撮影の時間がとられていた。昨年もそうだったが、しゃべり通しでさぞ疲れていらっしゃるだろうに、そんな気色は露も見せず、笑顔で応じていらっしゃった。
身体に流れているのは韓国人の血、生まれ育ったのは日本、といういわば2つの祖国を持つ銀瓶さんならではの韓国語落語。彼の韓国に対する思い、また日韓両国のますますの友好を願う彼の思いは、真摯な彼の姿勢からまっすぐに伝わってきた。
落語を始める前に、まずは韓国語で自己紹介。韓国人の祖父母と両親を持つ在日3世であること、師匠は笑福亭鶴瓶さんであること、東京には500人、大阪には200人の落語家がいるが、韓国語で落語をするのは日本で自分1人だけだということなどなど。
また、偶然にも今日5月25日は、落語家である彼にとって大切な記念日。
今から21年前の1988年5月25日、師匠である鶴瓶さんから 「銀瓶」 という名前をつけてもらった日なのだそうだ。
そんな記念日に、ご自身の祖国である韓国で落語の公演ができるのは、とても感慨深いことだろう。
さて、自己紹介のあとは、小咄をいくつか披露。
そしていよいよ、韓国語の落語。
落語というものは、話す内容を頭の中で想像しながら聴いてください、想像しながら仕草を見てください、とあらかじめ観客に伝える。
韓国語の落語、題目は 「개 눈(犬の目)」。
とても表情豊かに、また滑らかな韓国語で話される落語に、観客は自然と引き込まれ会場は笑いの渦。
昨年も感じたが、一体どれほどの努力と練習を積み重ねたのだろうかと心を打たれる。
昨年は、韓国語の落語を2本披露されたが、今年は韓国語の 「개 눈(犬の目)」 の次は、日本語で 「手水回し」 を披露された。「手水(ちょうず)」 のことを 「長・頭(ちょうず)=長い頭」 のことだと誤解したことによる大騒動。あらかじめ理解しておかないと意味が分からないキーワードを説明され、それをふまえた上で聴いてください、という配慮もされていた。
これまた大爆笑。
実に楽しい落語で、大いに笑わせてもらった。
韓国人にとっては、もちろん韓国語で話した 「개 눈(犬の目)」 の方が理解しやすかったはずだが、むしろ 「手水回し」 の方が客席の笑いは大きかったように感じた。
それだけ、言葉の壁を越えて伝わるものがあったということだろうか。
また余興として、会場となった釜慶大学の日本語学部の学生数人を舞台に上げ、落語を体験してもらうという場面もあった。彼ら学生は、落語を通して日本語を勉強するという授業も受けているのだそうだ。
1人ずつ舞台に上がった日本語学部の学生と、日本語で話しながら 「扇子を使ってうどんを食べる仕草」 や 「扇子を使ってタバコを吸っている仕草」 などを指導し、体験してもらうというもの。
こんなふうに楽しく過ごした時間も、いよいよ最後の挨拶となった。
自分には祖父母や両親と同じように、韓国人の血が流れている。韓国のことを祖国だと感じたくて韓国語を習い始め、韓国の人にも日本の伝統芸能を伝えたくて韓国語で落語をするようになった。
皆さんが韓国で日本に興味を持って日本語を勉強されているように、日本にも韓国に興味を持って韓国について勉強している人がたくさんいる。
このように、2つの国の人同士が、それぞれお互いに興味を持ち、お互いのことを知るという交流は本当に大切なことだと思う。また、韓国に落語をしに来ます。
会場は再び大きな拍手と歓声。
銀瓶さんが舞台から下りて、会場の出入り口へ歩いていこうとすると、あっという間に学生たち(特に女子学生)に取り囲まれ、写真攻撃を受けていた。
とても気さくな銀瓶さん、携帯のカメラを向ける女子大生たちに向かって、立ち止まって顔を彼女たちの方に突き出し、カメラポーズをするという場面も。
完全に四方を学生たちに”包囲”されてしまった銀瓶さん。
至近距離で携帯カメラのレンズを向ける女子学生たち。私も記念に1枚と思ったが、とてもとても正面からは近づける状態ではなかった。
この後も、会場を出たあたりでは長い間、記念写真撮影の時間がとられていた。昨年もそうだったが、しゃべり通しでさぞ疲れていらっしゃるだろうに、そんな気色は露も見せず、笑顔で応じていらっしゃった。
身体に流れているのは韓国人の血、生まれ育ったのは日本、といういわば2つの祖国を持つ銀瓶さんならではの韓国語落語。彼の韓国に対する思い、また日韓両国のますますの友好を願う彼の思いは、真摯な彼の姿勢からまっすぐに伝わってきた。
Posted by dilbelau at 11:55│Comments(0)
│文化・芸術・エンタメ