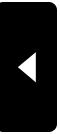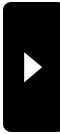2012年10月24日
『希望の国』
今年の釜山国際映画祭(BIFF)では、園子温監督の 『希望の国』 と、北朝鮮・イギリス・ベルギーの3国合作 『Comrade Kim Goes Flying(金同志は空を飛ぶ)』 の2つの作品を観た。
『希望の国』 はシンセゲ(新世界)百貨店7階にある 「CGVセンタムシティ」 のStarium館で観覧。

想像していた通りの重い、重い内容だった。登場人物らの怒りや憤り、悲しみ、やるせなさ、不安、絶望などの濃厚な感情や、どうしようもない現実を、直球で目の前に投げつけられた気がした。
映画を観た後、映画のHPの監督インタビューを読んでなるほどと思った。
-原発事故によって一家離散した方の話や、酪農家の方が自殺した話はいろいろなところで報道されましたよね。ニュースやドキュメンタリーが記録するのは“情報”です。でも、僕が記録したかったのは被災地の“情緒”や“情感”でした。それを描きたかったんです。
-別にメッセージ性のあるものを作りたかったわけじゃないんです。政治的な映画を作りたかったわけでもありません。原発がいいか悪いかという映画を撮っても、それは映画としてあまり有効でないような気がします。映画は、巨大な質問状を叩きつける装置なんです。だから、そこで起きていることを認識して、ただ映画にするだけで十分でした。そうすることで、見えてくるものがいくつもあるんじゃないかって。取材した場所の中には、もちろん壮絶な被害を被ったところもありましたが、一方でとても落ち着いている場所もある。だから、センセーショナルなものとして描きたくはありませんでした。
大震災と原発事故をモチーフにした映画だと聞き、是非観てみたいと思った。
大震災が起こったとき、私は釜山の職場(新聞社)で仕事中だった。
「日本が大変なことになっている」。
職場の同僚の言葉にうながされ、フロアに設置してある大型テレビの前に行った。津波がまちの全てを飲み込んでいく映像が流れていた。まるで映画の一場面のようで、これが現実の映像だとはにわかには信じがたかった。
その後も被災地の様子や原発事故のニュースは、テレビや新聞、インターネットなどを通して刻々と伝わってきた。しかし自分の国で起こっている出来事ながら、それを見る自分の目線が外国人のそれであるように感じられ、違和感を感じていた。どこか距離があるような。
そして、自分の国の出来事なのに、自分は直接的には放射能の影響を受けない外国にいて、遠いところからまるで他人事のように傍観しているかのような、後ろめたさや罪悪感も感じていた。しかし、そういう感情と正面から向き合うのは苦しいので、直視するのを無意識に避けていたように思う。
この映画を観ることで、原発事故に巻き込まれてしまった人々がどういう気持ちで、どういう生活を送っているのか、テレビや新聞からは伝わってこないような部分まで知ることができた気がする。もちろん映画で描かれていたのはごく一部で、現実にはああいうことが無数に起こっているのだろうが。実際に体験した人でないと分からない気持ちや感情をリアルに描き出していたと思う。
あらためて、こういうことは2度と起こってはならないと強く感じた。
『希望の国』 はシンセゲ(新世界)百貨店7階にある 「CGVセンタムシティ」 のStarium館で観覧。

想像していた通りの重い、重い内容だった。登場人物らの怒りや憤り、悲しみ、やるせなさ、不安、絶望などの濃厚な感情や、どうしようもない現実を、直球で目の前に投げつけられた気がした。
映画を観た後、映画のHPの監督インタビューを読んでなるほどと思った。
*****
-原発事故によって一家離散した方の話や、酪農家の方が自殺した話はいろいろなところで報道されましたよね。ニュースやドキュメンタリーが記録するのは“情報”です。でも、僕が記録したかったのは被災地の“情緒”や“情感”でした。それを描きたかったんです。
-別にメッセージ性のあるものを作りたかったわけじゃないんです。政治的な映画を作りたかったわけでもありません。原発がいいか悪いかという映画を撮っても、それは映画としてあまり有効でないような気がします。映画は、巨大な質問状を叩きつける装置なんです。だから、そこで起きていることを認識して、ただ映画にするだけで十分でした。そうすることで、見えてくるものがいくつもあるんじゃないかって。取材した場所の中には、もちろん壮絶な被害を被ったところもありましたが、一方でとても落ち着いている場所もある。だから、センセーショナルなものとして描きたくはありませんでした。
*****
大震災と原発事故をモチーフにした映画だと聞き、是非観てみたいと思った。
大震災が起こったとき、私は釜山の職場(新聞社)で仕事中だった。
「日本が大変なことになっている」。
職場の同僚の言葉にうながされ、フロアに設置してある大型テレビの前に行った。津波がまちの全てを飲み込んでいく映像が流れていた。まるで映画の一場面のようで、これが現実の映像だとはにわかには信じがたかった。
その後も被災地の様子や原発事故のニュースは、テレビや新聞、インターネットなどを通して刻々と伝わってきた。しかし自分の国で起こっている出来事ながら、それを見る自分の目線が外国人のそれであるように感じられ、違和感を感じていた。どこか距離があるような。
そして、自分の国の出来事なのに、自分は直接的には放射能の影響を受けない外国にいて、遠いところからまるで他人事のように傍観しているかのような、後ろめたさや罪悪感も感じていた。しかし、そういう感情と正面から向き合うのは苦しいので、直視するのを無意識に避けていたように思う。
この映画を観ることで、原発事故に巻き込まれてしまった人々がどういう気持ちで、どういう生活を送っているのか、テレビや新聞からは伝わってこないような部分まで知ることができた気がする。もちろん映画で描かれていたのはごく一部で、現実にはああいうことが無数に起こっているのだろうが。実際に体験した人でないと分からない気持ちや感情をリアルに描き出していたと思う。
あらためて、こういうことは2度と起こってはならないと強く感じた。
Posted by dilbelau at 08:44│Comments(0)
│釜山国際映画祭