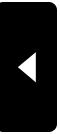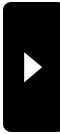2010年09月04日
名古屋海洋博物館
一時帰国していた日本から釜山へと戻る前日、夫と名古屋海洋博物館を訪れた。名古屋港水族館や南極観測船ふじの近くに建つ、名古屋港ポートビルの3~4階にある。入場大人300円。
名古屋港の生い立ちから現在の様子までを、実物やパノラマ模型、立体パネルや映像などで見ることができる。まず入り口を入ったところにドーンと展示されているのが、実物大のグラブバケット(▼)。名古屋港の浚渫・埋め立て工事に使われていたもののレプリカだそうだ。

いまや、三市一町一村(名古屋市・東海市・知多市・弥富町・飛島村)にまたがる広大な水面を有し、商業港と工業港の機能を兼ね備えた総合港湾となった名古屋港。しかし、本格的な港湾整備が始まったのは明治時代に入ってからだったそうだ。
それまでは名古屋港発祥の地とされる 「熱田の浜」 が船着き場としてにぎわっている程度だったが、1896(明治29)年、いよいよ熱田湾築港工事が開始された。
驚いたのは、この頃の熱田湾は水深が-1m程度で、一面を葦が覆う沼地のようだったということ。現在の名古屋港のもとの姿が、水深がそんなにも浅い沼地であったとは。
館内には、よく耳にする ”ブォ~ン” というエアホーンを実際に鳴らしてみることのできる擬似操縦席(▼)や、港で働く人々の様子を紹介するビデオ、船の模型など、大人も子供も楽しみながら学ぶことができるようになっている。


港で働く人々を紹介するビデオで、ギャングと呼ばれる人たちのことが取り上げられていた。輸出する自動車を、専用の船に積み込む作業をする15人一組のドライバーたちのことだ。
コンテナなどはガントリークレーン(▼)という機械で積込作業を行うことができるが、船内に自動車を積むのはどうしても人の手が必要になる。膨大な数の自動車を、できるだけ速く正確に船内に積み込むために、一糸乱れぬチームワークで働くその姿は、まさに職人技。積み込む自動車は、隣の自動車との間隔がドアとドアが10センチ、バンパーとバンパーが30センチになるように積み込む。ずらりと並んだ姿は圧巻だった。

(▲)ガントリークレーンを映像で体感できるようにした装置。
窓の外に広がる海ではウィンドサーフィンを楽しむ人たちの姿が。

名港トリトンの愛称で呼ばれる3つの橋のうちの、名港中央大橋(▼)。

こちらは、名古屋港の ”ハシケ” の模型(▼)。”尾張ダンベ” とも呼ばれていた名古屋港のハシケは、大型船が港に入港すると主に貨物の積卸をして目的地へ運ぶのに使用されていた。

ハシケの船頭やその家族は、船で寝起きをしながら生活をしていたが、小・中学生は児童寮に入ってそこから学校へ通い、土・日曜日はハシケに帰って来た。
年々港湾施設の整備が進むと共に、大型船も直接岸壁に接岸できるようになり、貨物も直接トラックに積み降ろしをして運ばれるようになったため、ハシケは年々少なくなり今ではハシケを見ることができなくなった。模型のハシケの上には、デッキを磨く父親・洗濯板で洗濯をする母親と子供の姿が見える。
こちらは昭和初期の名古屋港(▼)。この桟橋は昭和初期の頃、港内でけい船浮標を除いてただ一つの、大型船が接岸できる桟橋だった。鉄道も付設されており、輸出入貨物の積み降ろしに使用されていた。時には客船が桟橋に接岸し、見送る人々で賑わい、市民に親しまれていたのだそうだ。

「龍馬伝」 にも登場した黒船(▼)。これは1850年に建造された 「サスケハナ」 という名前の船。

1853年、日本に開国を求めて浦賀に来航したペリーの黒船艦隊の旗艦。ペリーはアメリカ大統領の親書を携え日本に開国を迫り、翌年に日米和親条約を締結させた。サスケハナは帆と蒸気機関を併用している。
ポートビルの3階と4階にまたがる名古屋海洋博物館。これら展示コーナーの他にも、子供が喜びそうな(大人も楽しんでやっていた)クイズコーナーや情報コーナーなどもあり、館内は予想以上に充実していた。
名古屋海洋博物館
名古屋市港区港町1番9号 名古屋港ポートビル3・4階
(052) 652-1111(名古屋みなと振興財団)
営業時間:9:30~17:00
定休日:月曜日(祝日の場合は翌日)
名古屋港の生い立ちから現在の様子までを、実物やパノラマ模型、立体パネルや映像などで見ることができる。まず入り口を入ったところにドーンと展示されているのが、実物大のグラブバケット(▼)。名古屋港の浚渫・埋め立て工事に使われていたもののレプリカだそうだ。
いまや、三市一町一村(名古屋市・東海市・知多市・弥富町・飛島村)にまたがる広大な水面を有し、商業港と工業港の機能を兼ね備えた総合港湾となった名古屋港。しかし、本格的な港湾整備が始まったのは明治時代に入ってからだったそうだ。
それまでは名古屋港発祥の地とされる 「熱田の浜」 が船着き場としてにぎわっている程度だったが、1896(明治29)年、いよいよ熱田湾築港工事が開始された。
驚いたのは、この頃の熱田湾は水深が-1m程度で、一面を葦が覆う沼地のようだったということ。現在の名古屋港のもとの姿が、水深がそんなにも浅い沼地であったとは。
館内には、よく耳にする ”ブォ~ン” というエアホーンを実際に鳴らしてみることのできる擬似操縦席(▼)や、港で働く人々の様子を紹介するビデオ、船の模型など、大人も子供も楽しみながら学ぶことができるようになっている。
港で働く人々を紹介するビデオで、ギャングと呼ばれる人たちのことが取り上げられていた。輸出する自動車を、専用の船に積み込む作業をする15人一組のドライバーたちのことだ。
コンテナなどはガントリークレーン(▼)という機械で積込作業を行うことができるが、船内に自動車を積むのはどうしても人の手が必要になる。膨大な数の自動車を、できるだけ速く正確に船内に積み込むために、一糸乱れぬチームワークで働くその姿は、まさに職人技。積み込む自動車は、隣の自動車との間隔がドアとドアが10センチ、バンパーとバンパーが30センチになるように積み込む。ずらりと並んだ姿は圧巻だった。
(▲)ガントリークレーンを映像で体感できるようにした装置。
窓の外に広がる海ではウィンドサーフィンを楽しむ人たちの姿が。
名港トリトンの愛称で呼ばれる3つの橋のうちの、名港中央大橋(▼)。
こちらは、名古屋港の ”ハシケ” の模型(▼)。”尾張ダンベ” とも呼ばれていた名古屋港のハシケは、大型船が港に入港すると主に貨物の積卸をして目的地へ運ぶのに使用されていた。
ハシケの船頭やその家族は、船で寝起きをしながら生活をしていたが、小・中学生は児童寮に入ってそこから学校へ通い、土・日曜日はハシケに帰って来た。
年々港湾施設の整備が進むと共に、大型船も直接岸壁に接岸できるようになり、貨物も直接トラックに積み降ろしをして運ばれるようになったため、ハシケは年々少なくなり今ではハシケを見ることができなくなった。模型のハシケの上には、デッキを磨く父親・洗濯板で洗濯をする母親と子供の姿が見える。
こちらは昭和初期の名古屋港(▼)。この桟橋は昭和初期の頃、港内でけい船浮標を除いてただ一つの、大型船が接岸できる桟橋だった。鉄道も付設されており、輸出入貨物の積み降ろしに使用されていた。時には客船が桟橋に接岸し、見送る人々で賑わい、市民に親しまれていたのだそうだ。
「龍馬伝」 にも登場した黒船(▼)。これは1850年に建造された 「サスケハナ」 という名前の船。
1853年、日本に開国を求めて浦賀に来航したペリーの黒船艦隊の旗艦。ペリーはアメリカ大統領の親書を携え日本に開国を迫り、翌年に日米和親条約を締結させた。サスケハナは帆と蒸気機関を併用している。
ポートビルの3階と4階にまたがる名古屋海洋博物館。これら展示コーナーの他にも、子供が喜びそうな(大人も楽しんでやっていた)クイズコーナーや情報コーナーなどもあり、館内は予想以上に充実していた。
名古屋海洋博物館
名古屋市港区港町1番9号 名古屋港ポートビル3・4階
(052) 652-1111(名古屋みなと振興財団)
営業時間:9:30~17:00
定休日:月曜日(祝日の場合は翌日)
Posted by dilbelau at 21:22│Comments(0)
│日本