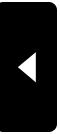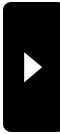2013年08月11日
活版印刷の仕組み 25
つづき
新聞制作に必要な機械類の展示もあり、新聞制作の過程がよく分かって興味深かった。
鉛の活字は1度使うとすり減るため、使用後は毎回溶かしてあらたに活字を鋳造し直していた。写真右奥は 「自動活字鋳造機」(▼)。1960年代中盤、1日8面の紙面で発行されていた新聞を印刷するには、約15万字の鉛の活字が必要で、それを毎日鋳造していた。手前の木箱は、「本母型函」。自動活字鋳造機は、溶かした鉛を母型に流し込んで活字を作る。
左奥は 「文選台」。鋳造された鉛の活字は、大きさや順序別に木箱に入れ、文選台に並べる。活字の使用頻度によって、よく使う活字は届きやすいところに、あまり使わない活字は遠いところに並べた。熟練した文選工は1分に約40字を選び出すことができたが、字を崩して書いた原稿を判読するのに時間がかかるため、平均するとだいたい1分に20字ほど選び出していた。

木製カメラ(▼)。写真の製版は銅板の上に大小の点を化学薬品で扶植させてイメージを再生する技術。漫画や気象図、地図などの絵や写真などはこの方法で、別に銅版を作った。

組版にインクをつける台(右)と自動校正紙印刷機(奥)(▼)。組版したものをこの印刷機で印刷し、校閲する。

校閲後、記事ごとの版を組む小組台(▼)。台の上にのっているのは小組完了版。

小組完了版を組み合わせて大組版(▼)をつくる。

紙型加湿器(右)と紙型圧縮機(左▼)。紙型とは表面に樹脂を塗った特殊な紙が何重にも重なっている厚い紙のこと。湿り気を加えた紙型に、組版された新聞の内容を凹型に刻んで乾燥させる。
紙型(左)と亜鉛やすずを溶かす釜(右)、紙型乾燥機(奥▼)。

次に300℃の亜鉛、すず、アンチモンを合金したものを紙型に流しかけて鋳造し、新聞を印刷する鉛版(▼)を作る。鉛版は輪転機に掛けられるよう、円筒を半分にした形をしている。鉛版をいくつか作って印刷機に同時に掛ければ、短時間で多くの部数を印刷することができ、活字の摩耗も少なく印刷状態もよい。

ロールスタンドと紙(右)と、輪転機(左▼)。1863年にロールスタンドの技術が開発されるまでは、いちいち紙を裁断して輪転機に挿入していた。

鉛版を輪転機に掛けて印刷することを輪転印刷と呼ぶ。印刷過程は給紙・輪転・切紙、そして紙を折るという作業に分かれる。印刷機の中には反対方向に回転する2つのシリンダーの間を紙が通過し、印刷されていく。
新聞が印刷されるまでの流れがよく分かって、とても面白かった。
つづく
新聞制作に必要な機械類の展示もあり、新聞制作の過程がよく分かって興味深かった。
鉛の活字は1度使うとすり減るため、使用後は毎回溶かしてあらたに活字を鋳造し直していた。写真右奥は 「自動活字鋳造機」(▼)。1960年代中盤、1日8面の紙面で発行されていた新聞を印刷するには、約15万字の鉛の活字が必要で、それを毎日鋳造していた。手前の木箱は、「本母型函」。自動活字鋳造機は、溶かした鉛を母型に流し込んで活字を作る。
左奥は 「文選台」。鋳造された鉛の活字は、大きさや順序別に木箱に入れ、文選台に並べる。活字の使用頻度によって、よく使う活字は届きやすいところに、あまり使わない活字は遠いところに並べた。熟練した文選工は1分に約40字を選び出すことができたが、字を崩して書いた原稿を判読するのに時間がかかるため、平均するとだいたい1分に20字ほど選び出していた。
木製カメラ(▼)。写真の製版は銅板の上に大小の点を化学薬品で扶植させてイメージを再生する技術。漫画や気象図、地図などの絵や写真などはこの方法で、別に銅版を作った。
組版にインクをつける台(右)と自動校正紙印刷機(奥)(▼)。組版したものをこの印刷機で印刷し、校閲する。
校閲後、記事ごとの版を組む小組台(▼)。台の上にのっているのは小組完了版。
小組完了版を組み合わせて大組版(▼)をつくる。
紙型加湿器(右)と紙型圧縮機(左▼)。紙型とは表面に樹脂を塗った特殊な紙が何重にも重なっている厚い紙のこと。湿り気を加えた紙型に、組版された新聞の内容を凹型に刻んで乾燥させる。
紙型(左)と亜鉛やすずを溶かす釜(右)、紙型乾燥機(奥▼)。
次に300℃の亜鉛、すず、アンチモンを合金したものを紙型に流しかけて鋳造し、新聞を印刷する鉛版(▼)を作る。鉛版は輪転機に掛けられるよう、円筒を半分にした形をしている。鉛版をいくつか作って印刷機に同時に掛ければ、短時間で多くの部数を印刷することができ、活字の摩耗も少なく印刷状態もよい。
ロールスタンドと紙(右)と、輪転機(左▼)。1863年にロールスタンドの技術が開発されるまでは、いちいち紙を裁断して輪転機に挿入していた。
鉛版を輪転機に掛けて印刷することを輪転印刷と呼ぶ。印刷過程は給紙・輪転・切紙、そして紙を折るという作業に分かれる。印刷機の中には反対方向に回転する2つのシリンダーの間を紙が通過し、印刷されていく。
新聞が印刷されるまでの流れがよく分かって、とても面白かった。
つづく
Posted by dilbelau at 08:34│Comments(0)
│ソウル