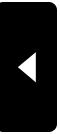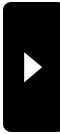2010年05月21日
'10.5.21(金)お釈迦様の生誕日
今日5月21日は 「お釈迦様の生誕日」 で、韓国では祝日だ。
といっても毎年5月21日であるというわけではなく、陰暦の4月8日と定められているので、陽暦でそれが何月何日に当たるかは毎年異なる。昨年は5月2日だった。
余談だが、韓国ではこの 「お釈迦様の生誕日」 が祝日であるのと同様、「イエス・キリストの生誕日」 である12月25日も、祝日である。
さて、この 「お釈迦様の生誕日」 には、大きなお寺では参拝客に簡単な食事の振る舞いをする習慣があると聞き、夫と2人で家からそう遠くない 「옥련선원(玉蓮禅院)」 へ行ってみた。以前、Sオンニから教えてもらったお寺だ。
お寺の近くまで来ると、ピーピーとけたたましく笛を鳴らしながら交通整理が行なわれている。6月2日の地方選挙が近づいてき、選挙カーに乗っての選挙活動が盛んになってきているので、その影響による渋滞緩和をしているのかと思いきや、なんのことはない、私たちが目指している 「玉蓮禅院」 をマイカーやタクシーで訪れる人たちのための交通整理だったのだ。
お寺へと続く坂道には大勢の人たち。今から行く人もいれば、もう下りてきている人も。今年の元日、初詣代わりに夫と訪れたときよりも、はるかに多い人出だ。

この日、お寺にはこのように大勢の人が訪れることを見越して、選挙活動に来ている支援者の姿もたくさん見られた。それぞれ各政党のイメージカラーのTシャツを着て、写真入りの候補者の名刺を配っている。

山門をくぐってさらに坂道を上っていく途中には、いろいろなものを売る露天商が並んでいる。日本でも、縁日などのときに屋台がたくさん並ぶのと同じような感じだ。
写真手前(▼)に見えている、茶色い四角いものは 「도토리 묵(トットリ ムッ)」 と言って、どんぐりで作った寒天状の食品。そして向こうに見える赤いザルで売られているのは、私の天敵 「번데기(ポンテギ)」。蚕のさなぎを煮付けたものだ。「糖尿・便秘・貧血によい」 と書いてあり、確かに美容にいいとされ女性も好んでよく食べているが、私は1度食べてギブアップ・・・。

こちら(▼)は솜사탕(綿菓子)。このように、アイスコーヒーなどを入れるプラスティックの容器に入れて売っているのもよく見かける。

おじさんが売っているのは竹細工(▼)。おじさんの後ろに見えている半球形のものは、食べ物の蝿・虫よけだろう。向こうでおばさんがかがんで見ているのは昆布。

つづく
といっても毎年5月21日であるというわけではなく、陰暦の4月8日と定められているので、陽暦でそれが何月何日に当たるかは毎年異なる。昨年は5月2日だった。
余談だが、韓国ではこの 「お釈迦様の生誕日」 が祝日であるのと同様、「イエス・キリストの生誕日」 である12月25日も、祝日である。
さて、この 「お釈迦様の生誕日」 には、大きなお寺では参拝客に簡単な食事の振る舞いをする習慣があると聞き、夫と2人で家からそう遠くない 「옥련선원(玉蓮禅院)」 へ行ってみた。以前、Sオンニから教えてもらったお寺だ。
お寺の近くまで来ると、ピーピーとけたたましく笛を鳴らしながら交通整理が行なわれている。6月2日の地方選挙が近づいてき、選挙カーに乗っての選挙活動が盛んになってきているので、その影響による渋滞緩和をしているのかと思いきや、なんのことはない、私たちが目指している 「玉蓮禅院」 をマイカーやタクシーで訪れる人たちのための交通整理だったのだ。
お寺へと続く坂道には大勢の人たち。今から行く人もいれば、もう下りてきている人も。今年の元日、初詣代わりに夫と訪れたときよりも、はるかに多い人出だ。
この日、お寺にはこのように大勢の人が訪れることを見越して、選挙活動に来ている支援者の姿もたくさん見られた。それぞれ各政党のイメージカラーのTシャツを着て、写真入りの候補者の名刺を配っている。
山門をくぐってさらに坂道を上っていく途中には、いろいろなものを売る露天商が並んでいる。日本でも、縁日などのときに屋台がたくさん並ぶのと同じような感じだ。
写真手前(▼)に見えている、茶色い四角いものは 「도토리 묵(トットリ ムッ)」 と言って、どんぐりで作った寒天状の食品。そして向こうに見える赤いザルで売られているのは、私の天敵 「번데기(ポンテギ)」。蚕のさなぎを煮付けたものだ。「糖尿・便秘・貧血によい」 と書いてあり、確かに美容にいいとされ女性も好んでよく食べているが、私は1度食べてギブアップ・・・。
こちら(▼)は솜사탕(綿菓子)。このように、アイスコーヒーなどを入れるプラスティックの容器に入れて売っているのもよく見かける。
おじさんが売っているのは竹細工(▼)。おじさんの後ろに見えている半球形のものは、食べ物の蝿・虫よけだろう。向こうでおばさんがかがんで見ているのは昆布。
つづく
Posted by dilbelau at 18:32│Comments(0)
│その他寺院・城址