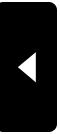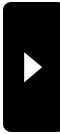2012年12月05日
落語と浪曲の世界
11月23日、釜慶(プギョン)大学で、国際交流基金の 「日本文化講座」 の1つ 「ことばの力 / 落語と浪曲の世界」 が開かれると聞き、夫と参加した。講座は19時開始とのことなので、大学近くの 「La lieto」 で先に夕食を済ませ、会場へ。

会場付近で偶然、日本語を流暢に話す韓国人の友人2人に出会った。やはりこの講演を聴きに来られたとのこと。今回の講演は、落語や浪曲はもちろん進行も全て日本語で行われるとのことだったが、200席のホールはほぼ満席。ほとんどは韓国人だった。友人の1人は、釜山で落語を聞くのはこれで3度目だそう。釜山で日本の伝統芸能をナマで見られる機会は少ないので、この講座は韓国人にとっても日本人にとってもいい機会だ。
講演は事前予約制。座席は指定されており、受付で受け取った座席番号に従って着席する。私たちの座席は何と最前列だった。申し込んだ時期が早かったからだろうか。最前列の座席には、私たちの席以外は番号ではなく名前が貼り付けてある。来賓・貴賓用の列のようで、数席隣は余田幸夫総領事の席。そんな中に私たちがまじって場違いのような感じがしたが、おかげでステージが間近で見られてよかった。
ステージには落語用の高座が設けられている。落語といえば、2009年5月、釜山で笑福亭銀瓶さんが披露してくれた韓国語と日本語の落語を思い出す。特に韓国語での落語は非常に素晴らしく、いたく感動した。
まず、国際交流基金の方の挨拶に続き、この講座を進行する民族・伝統芸能プロデューサーの中坪功雄さん(公益社団法人全日本郷土芸能協会の常任理事)の解説が始まった。「ことばの芸」 としての落語や浪曲、民謡について、その歴史や特徴などを分かりやすくレクチャーしてくださった。
そしていよいよ、林家ひろ木さんの落語が始まる。広島県庄原市出身の林家ひろ木さんは2002年に林家木久扇(当時の林家木久蔵)さんに入門し、2003年に 「二つ目」(前座と真打の間)に昇進したそうだ。
高座に上がって、まずは落語で使う道具(手ぬぐい、扇子)や動作(一人二役、歩く・走る様子)などを面白おかしく説明。早くも会場は笑いに包まれ雰囲気が和らいだ。この日は 「初天神」・「時そば」・「動物園」 の3つの演題のうち1つを上演する予定だったが、中坪さんによると、ひろ木さんは道具などを説明していたこのときに3つのうちどの演題を上演するか、観客の反応を見て決めていたそうだ。
この日は 「初天神」 を上演。ひろ木さんの話術であっという間に物語の中に引き込まれる。会場の反応もよい。日本語のセリフを完全には理解できなくても、身振り手振りがついてくるので韓国人にとっても楽しみやすいだろうと思う。とても面白かった。
続いて片倉京子さんの民謡。茨城県境町出身の片倉さんは、民謡の神様として知られた初代浜田喜一一座の旅芸人として、子どもの頃から各地を巡業していたそう。その中で、日本舞踊や長唄、三味線、浪曲、端唄、小唄、俗曲、民謡などの芸の基本を習得したそうだ。
また、1967年から津軽三味線も習い始め、高橋流名取(芸名・ゆきじ)となった。現在は民謡教室を開く傍ら、浪曲の曲師として活躍しているそうだ。
美しい淡い桃色の着物姿で登場した片倉さんは、小柄ながら存在感たっぷり。「黒田節」と「長崎ぶらぶら節」、「秋田荷方(にかた)節」の3曲を、三味線を弾きながら歌われた。それぞれの曲についての説明もしてくれたので、より興味を持って聴くことができた。
普通は、三味線を弾くか、歌うかのどちらかだけをするものだそうで、片倉さんのように三味線を弾きながら歌うというのは至難の業なのだそうだ。特に最後の 「秋田荷方節」 は今で言うラップのような曲だそうで、三味線を弾くだけでも相当難しいとのこと。テンポも速くバチを持つ右手がつりそうになるほどだそうだ。そこに歌もつけるのだから相当なものだ。
3曲を演奏し終えて、客席からリクエストを受け付けますとのことだったが、私も含めて観客のほとんどが 「どんな曲をリクエストしていよいか分からない」 状態だったようで、リクエストが出なかった。すると、「じゃあリクエストがないようなので・・・」 と片倉さんが豊富なレパートリーの中から1曲披露してくれた。曲の途中で 「アリラン」 もアレンジして弾き込むと、客席からは歌声が。大好評。
そして 「お仲入り」(休憩)をはさんで最後は玉川太福(だいふく)さんの浪曲。新潟県新潟市出身の玉川さんは、2007年に二代目玉川福太郎に入門、福太郎が得意とした古典演題を継承しながら、自らコントを上演したり映像作品に参加したりしているそうだ。
この日の演題は 「阿武松(おおのまつ)」。曲師は片倉京子さん。私にとって浪曲は、「何かで少し耳にしたことはあるかもしれないが記憶も薄く、どんなものかもよく知らない」 という存在。この日のようにナマで、しかも目の前でしっかり聴くのは初めてだった。
事前に夫から 「“旅ぃ~ゆけぇば~駿河のぉ~・・・” とか言うあれが浪曲だよ」 と聞き、難しくて言葉も理解できないかもしれないと思っていたが、大きな間違いだった。
非常に面白く、落語同様、一気に物語に引き込まれる。日本で1920年代にラジオ放送が普及し始めると、全国どこに行ってもラジオから浪曲が流れ、日本人にとってなくてはならない大衆娯楽として定着したそうだが、まさに現代のテレビ・映画だ。表情豊かに語る太福さんの世界にすっかり魅せられた。主人公の大食漢ぶりに、他人事とは思えないような共感も感じつつ・・・。最後も、ほどよい余韻を残しての幕引き。とても面白かった。
最後に、3人がステージに並んで質疑応答の時間。落語も民謡も浪曲も、いずれも師匠から弟子へと口伝えで伝えられていく芸能。その難しさを面白おかしく紹介してくれた。とても楽しい貴重な時間を過ごすことができた。

会場付近で偶然、日本語を流暢に話す韓国人の友人2人に出会った。やはりこの講演を聴きに来られたとのこと。今回の講演は、落語や浪曲はもちろん進行も全て日本語で行われるとのことだったが、200席のホールはほぼ満席。ほとんどは韓国人だった。友人の1人は、釜山で落語を聞くのはこれで3度目だそう。釜山で日本の伝統芸能をナマで見られる機会は少ないので、この講座は韓国人にとっても日本人にとってもいい機会だ。
講演は事前予約制。座席は指定されており、受付で受け取った座席番号に従って着席する。私たちの座席は何と最前列だった。申し込んだ時期が早かったからだろうか。最前列の座席には、私たちの席以外は番号ではなく名前が貼り付けてある。来賓・貴賓用の列のようで、数席隣は余田幸夫総領事の席。そんな中に私たちがまじって場違いのような感じがしたが、おかげでステージが間近で見られてよかった。
ステージには落語用の高座が設けられている。落語といえば、2009年5月、釜山で笑福亭銀瓶さんが披露してくれた韓国語と日本語の落語を思い出す。特に韓国語での落語は非常に素晴らしく、いたく感動した。
まず、国際交流基金の方の挨拶に続き、この講座を進行する民族・伝統芸能プロデューサーの中坪功雄さん(公益社団法人全日本郷土芸能協会の常任理事)の解説が始まった。「ことばの芸」 としての落語や浪曲、民謡について、その歴史や特徴などを分かりやすくレクチャーしてくださった。
そしていよいよ、林家ひろ木さんの落語が始まる。広島県庄原市出身の林家ひろ木さんは2002年に林家木久扇(当時の林家木久蔵)さんに入門し、2003年に 「二つ目」(前座と真打の間)に昇進したそうだ。
高座に上がって、まずは落語で使う道具(手ぬぐい、扇子)や動作(一人二役、歩く・走る様子)などを面白おかしく説明。早くも会場は笑いに包まれ雰囲気が和らいだ。この日は 「初天神」・「時そば」・「動物園」 の3つの演題のうち1つを上演する予定だったが、中坪さんによると、ひろ木さんは道具などを説明していたこのときに3つのうちどの演題を上演するか、観客の反応を見て決めていたそうだ。
この日は 「初天神」 を上演。ひろ木さんの話術であっという間に物語の中に引き込まれる。会場の反応もよい。日本語のセリフを完全には理解できなくても、身振り手振りがついてくるので韓国人にとっても楽しみやすいだろうと思う。とても面白かった。
続いて片倉京子さんの民謡。茨城県境町出身の片倉さんは、民謡の神様として知られた初代浜田喜一一座の旅芸人として、子どもの頃から各地を巡業していたそう。その中で、日本舞踊や長唄、三味線、浪曲、端唄、小唄、俗曲、民謡などの芸の基本を習得したそうだ。
また、1967年から津軽三味線も習い始め、高橋流名取(芸名・ゆきじ)となった。現在は民謡教室を開く傍ら、浪曲の曲師として活躍しているそうだ。
美しい淡い桃色の着物姿で登場した片倉さんは、小柄ながら存在感たっぷり。「黒田節」と「長崎ぶらぶら節」、「秋田荷方(にかた)節」の3曲を、三味線を弾きながら歌われた。それぞれの曲についての説明もしてくれたので、より興味を持って聴くことができた。
普通は、三味線を弾くか、歌うかのどちらかだけをするものだそうで、片倉さんのように三味線を弾きながら歌うというのは至難の業なのだそうだ。特に最後の 「秋田荷方節」 は今で言うラップのような曲だそうで、三味線を弾くだけでも相当難しいとのこと。テンポも速くバチを持つ右手がつりそうになるほどだそうだ。そこに歌もつけるのだから相当なものだ。
3曲を演奏し終えて、客席からリクエストを受け付けますとのことだったが、私も含めて観客のほとんどが 「どんな曲をリクエストしていよいか分からない」 状態だったようで、リクエストが出なかった。すると、「じゃあリクエストがないようなので・・・」 と片倉さんが豊富なレパートリーの中から1曲披露してくれた。曲の途中で 「アリラン」 もアレンジして弾き込むと、客席からは歌声が。大好評。
そして 「お仲入り」(休憩)をはさんで最後は玉川太福(だいふく)さんの浪曲。新潟県新潟市出身の玉川さんは、2007年に二代目玉川福太郎に入門、福太郎が得意とした古典演題を継承しながら、自らコントを上演したり映像作品に参加したりしているそうだ。
この日の演題は 「阿武松(おおのまつ)」。曲師は片倉京子さん。私にとって浪曲は、「何かで少し耳にしたことはあるかもしれないが記憶も薄く、どんなものかもよく知らない」 という存在。この日のようにナマで、しかも目の前でしっかり聴くのは初めてだった。
事前に夫から 「“旅ぃ~ゆけぇば~駿河のぉ~・・・” とか言うあれが浪曲だよ」 と聞き、難しくて言葉も理解できないかもしれないと思っていたが、大きな間違いだった。
非常に面白く、落語同様、一気に物語に引き込まれる。日本で1920年代にラジオ放送が普及し始めると、全国どこに行ってもラジオから浪曲が流れ、日本人にとってなくてはならない大衆娯楽として定着したそうだが、まさに現代のテレビ・映画だ。表情豊かに語る太福さんの世界にすっかり魅せられた。主人公の大食漢ぶりに、他人事とは思えないような共感も感じつつ・・・。最後も、ほどよい余韻を残しての幕引き。とても面白かった。
最後に、3人がステージに並んで質疑応答の時間。落語も民謡も浪曲も、いずれも師匠から弟子へと口伝えで伝えられていく芸能。その難しさを面白おかしく紹介してくれた。とても楽しい貴重な時間を過ごすことができた。
Posted by dilbelau at 08:54│Comments(0)
│文化・芸術・エンタメ