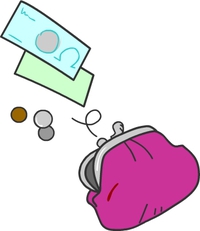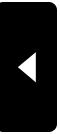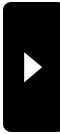2012年04月30日
ハングルの教科書 4
つづき
これは今回の展示会で展示されていたものではないが、チアチア族がハングルを公用文字として採択した2009年当時、チアチア族の小学生用に作られた教科書(連合ニュースより▼)。

チアチア族の言葉が、ハングルで表記されている。

この教科書は、ソウル大学言語学科の이호영(イ・ホヨン)教授主導のもとに作られたそう。以下、2009年12月21日連合ニュースに掲載されていた、イ・ホヨン教授のインタビュー(▼)。

Q. ハングルの普及は、現在どういう段階にあるか。
A. まだ初期の段階。チアチア語をハングルで教えている小学校が1校と、韓国語を教えている高校が1校ずつある。難しいこともあるが、現地ではうまくいっていると評価されている。今頃はほとんどの生徒が、ハングルを書いたり簡単な会話ができるくらい上達してると思う。バウバウ市が、ハングル普及を予定より早く拡大していきたいという意思を示しており、来年からは他の学校でも同じような教育を行う予定。
Q. 最近、釜山のある奉仕団体がチアチア族の教育基金を作るなど、いろいろなところで後援の動きが見られているそうだが。
A. 韓国教育放送公社(EBS)から、奨学基金として200万ウォンを提供していただけるとのこと。中古のコンピューター約300台を無償で提供するという機関もある。チアチア族の歴史や文化、古典文学などの書籍を編纂する費用として100万ウォン出すという個人もいる。
Q. ハングルの普及と土着語の存続は、国民の統合の妨げになり得るという見解のため、インドネシア政府の反応が心配だが。
A. インドネシア政府ははじめ、かなり戸惑っていたというのは事実。国内外のマスコミにたくさん報道され、その中で国民の多くが言葉と文字を混同した。
固有語を表記するためにハングルを採択したということなのに、まるで韓国語が固有語に取って代わるかのように勘違いし、インドネシアを文化的に侵略しようとしているかのように受け取られ困った。
現在は、ハングルで表記することで文化の保存・発展に協力し、インドネシアの国内法や国民統合の妨げにならない範囲で推進するという意思をはっきりさせているので、大きな問題はない状況。
Q. 他の地域の反発や宗教的な理由などによる、テロの危険などはないのか。
A. この地域はとても安全なエリア。イスラムの地域なので、他の宗教を布教しようとすれば問題になるが、われわれは現地の人々の文化を最大限尊重して今回の事業を推進していくつもり。
Q. ソウル市とバウバウ市の文化・芸術交流拡大のため、了解覚書(MOU)を締結した意味は。
A. 地方政府が国際協力関係を結ぶということ。文化・芸術の交流や、公務員の交換派遣などを行う予定。ソウル市もチアチア族の文化を韓国の国民に紹介したりして、お互いに協力していこうという計画。
Q. チアチア族以外に、他の種族からハングルに関して問い合わせが来たことはあるか。
A. バウバウ市側に、いくつか非公式に話が来たことがあるらしいが、私たちのところまでは話が届いていない。今はまずチアチア族の中でしっかりハングルを定着させることが重要だと思う。
Q. 今回の訪問は、バウバウ市とチアチア族にとってどんな意味があるのか。
A. 昨年、バウバウ市役所の公務員が6人ほど来たが、これまで外国に行く機会がなかった人にとって、どんな国だろうと思っていた韓国を実際に訪れたのは、地域社会に相当なインパクトがある。韓国は、こういうふうに暮らそうというモチベーションを彼らに与えられる国だと思う。
Q. 韓国が援助をエサに、チアチア族をそそのかしたと見る人もいるかもしれないが。
A. 我々は、はじめから金銭的な投資ができる立場にはないという点を、はっきり伝えていた。現地の、文字のない言語を研究することで、文化の保存と発展に寄与したいということだ。そういう誤解は道理に当てはまらない。
インドネシアでも、田舎なので貧しく食べ物も満足に食べられず、文化も劣っているだろうと考えられることもあるが、それは間違い。文化レベルや教育熱が高く、思考方法や行動パターンのレベルも相当高い。何より、インドネシアは人口2億4,000万以上の大国で有望な国だ。
A. チアチア族へのハングル普及事業が直面している、最大の問題や課題は。
Q. たくさんの方に支援していただき、これからもうまくいくと思う。今後も活動を成功させるためには、現地で教員養成もすべき。このたび韓国人教師も派遣する。現地の人々が自分たちの歴史や文化、口承文学などを文字で書き残すという作業を支援するという部分にも重点を置かなければならない。
これは今回の展示会で展示されていたものではないが、チアチア族がハングルを公用文字として採択した2009年当時、チアチア族の小学生用に作られた教科書(連合ニュースより▼)。

チアチア族の言葉が、ハングルで表記されている。

この教科書は、ソウル大学言語学科の이호영(イ・ホヨン)教授主導のもとに作られたそう。以下、2009年12月21日連合ニュースに掲載されていた、イ・ホヨン教授のインタビュー(▼)。

Q. ハングルの普及は、現在どういう段階にあるか。
A. まだ初期の段階。チアチア語をハングルで教えている小学校が1校と、韓国語を教えている高校が1校ずつある。難しいこともあるが、現地ではうまくいっていると評価されている。今頃はほとんどの生徒が、ハングルを書いたり簡単な会話ができるくらい上達してると思う。バウバウ市が、ハングル普及を予定より早く拡大していきたいという意思を示しており、来年からは他の学校でも同じような教育を行う予定。
Q. 最近、釜山のある奉仕団体がチアチア族の教育基金を作るなど、いろいろなところで後援の動きが見られているそうだが。
A. 韓国教育放送公社(EBS)から、奨学基金として200万ウォンを提供していただけるとのこと。中古のコンピューター約300台を無償で提供するという機関もある。チアチア族の歴史や文化、古典文学などの書籍を編纂する費用として100万ウォン出すという個人もいる。
Q. ハングルの普及と土着語の存続は、国民の統合の妨げになり得るという見解のため、インドネシア政府の反応が心配だが。
A. インドネシア政府ははじめ、かなり戸惑っていたというのは事実。国内外のマスコミにたくさん報道され、その中で国民の多くが言葉と文字を混同した。
固有語を表記するためにハングルを採択したということなのに、まるで韓国語が固有語に取って代わるかのように勘違いし、インドネシアを文化的に侵略しようとしているかのように受け取られ困った。
現在は、ハングルで表記することで文化の保存・発展に協力し、インドネシアの国内法や国民統合の妨げにならない範囲で推進するという意思をはっきりさせているので、大きな問題はない状況。
Q. 他の地域の反発や宗教的な理由などによる、テロの危険などはないのか。
A. この地域はとても安全なエリア。イスラムの地域なので、他の宗教を布教しようとすれば問題になるが、われわれは現地の人々の文化を最大限尊重して今回の事業を推進していくつもり。
Q. ソウル市とバウバウ市の文化・芸術交流拡大のため、了解覚書(MOU)を締結した意味は。
A. 地方政府が国際協力関係を結ぶということ。文化・芸術の交流や、公務員の交換派遣などを行う予定。ソウル市もチアチア族の文化を韓国の国民に紹介したりして、お互いに協力していこうという計画。
Q. チアチア族以外に、他の種族からハングルに関して問い合わせが来たことはあるか。
A. バウバウ市側に、いくつか非公式に話が来たことがあるらしいが、私たちのところまでは話が届いていない。今はまずチアチア族の中でしっかりハングルを定着させることが重要だと思う。
Q. 今回の訪問は、バウバウ市とチアチア族にとってどんな意味があるのか。
A. 昨年、バウバウ市役所の公務員が6人ほど来たが、これまで外国に行く機会がなかった人にとって、どんな国だろうと思っていた韓国を実際に訪れたのは、地域社会に相当なインパクトがある。韓国は、こういうふうに暮らそうというモチベーションを彼らに与えられる国だと思う。
Q. 韓国が援助をエサに、チアチア族をそそのかしたと見る人もいるかもしれないが。
A. 我々は、はじめから金銭的な投資ができる立場にはないという点を、はっきり伝えていた。現地の、文字のない言語を研究することで、文化の保存と発展に寄与したいということだ。そういう誤解は道理に当てはまらない。
インドネシアでも、田舎なので貧しく食べ物も満足に食べられず、文化も劣っているだろうと考えられることもあるが、それは間違い。文化レベルや教育熱が高く、思考方法や行動パターンのレベルも相当高い。何より、インドネシアは人口2億4,000万以上の大国で有望な国だ。
A. チアチア族へのハングル普及事業が直面している、最大の問題や課題は。
Q. たくさんの方に支援していただき、これからもうまくいくと思う。今後も活動を成功させるためには、現地で教員養成もすべき。このたび韓国人教師も派遣する。現地の人々が自分たちの歴史や文化、口承文学などを文字で書き残すという作業を支援するという部分にも重点を置かなければならない。
Posted by dilbelau at 08:57│Comments(0)
│その他いろいろ