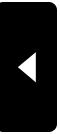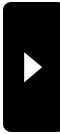2012年04月15日
水営野遊の始まり、始まり 10
つづき
영남교방청춤보존회(嶺南教坊庁舞保存会)の舞、부산농악(釜山農楽)の演奏・舞に続いて、수영야류(水営野遊=スヨンヤリュ)が披露される。
「水営野遊 保存会」 会長 김성율(金成律=キム・ソンユル)氏の、水営野遊の由来に関する説明(水営民俗保存会HPより)(▼)。
口承によれば、数百年前に慶尚左道・水軍節度使営が駐屯したとき、水使が陜川(ハプチョン)草溪(チョゲ)栗旨里(パンマリ)(現、慶南 陜川郡 徳谷面 栗旨里)の竹広大牌(デグァンデペ)の五広大(オグァンデ)を招いて踊らせたことから始まったという説と、水営の人々が栗旨里で(劇を)観て始まったという説がある。その当時の水営野遊の踊り手(ノリクン)は水営地方の生え抜きで、庶民や中間階層(ヤンバンと庶民の間の階層)の中で最も歌舞に長けていた人だった。
この地域で歌舞に長けている人のほとんどは、生活に余裕があって風流を楽しみ、周囲からも認められた人物だった。水営野遊は生え抜きによる代表的な탈놀음(タルノル厶=仮面劇)だった。
들놀음(トゥルノルム=野遊び)である水営野遊は、水営地方の農耕儀礼から自生的に発生して演劇へと発達しながら、朝鮮後期に떠돌이 탈놀음(トドリ タルノルム=流れ者仮面劇)の影響を受け、現在のような劇に発展したと思われる。
特に水営は海に接しているため、漁をするときに行われる漁労謡・踊りと、農作業をするときの農謡・踊りなどがその原型となっている。
また生活と踊りは互いに影響を及ぼしていた。生活の中に踊りがあり、踊りの文化は生活文化の延長線上にあった。踊りはすなわち生活であり、生活は踊りにつながるという美的構造をもとに、水営野遊は当時の生活像を反映していた。踊りそのものが彼らの生活へと通じていた。
そのため、水営野遊の덧배기(トッベギ)踊りは、ある特定の人の専門的な踊りではなく、大衆の中に自然発生的に生じたものである。飾り気のない身体の動きがリズムに乗って踊りへと昇華された。生活と密着しながら発展していった生活舞踊といえる。
このような、本能的で人間的な純粋舞踊のスタイルが、劇としてすでに特化していた水営野遊の中に溶けこんでいった。そして 「歌・舞・戯」 という3大要素から成る美的構造を作りながら、より土俗性の濃い踊りになっていった。水営野遊は、들놀음(トゥルノルム)という韓国仮面劇のルーツとも言える。
まずは、登場人物全員のパレードから。

提灯行列(▼)。昔は旧正月の月が昇る頃に行われていたため、提灯に先導されていた。


水営野遊は、第1幕 「양반과장(両班/ヤンバン科場)」、第2幕 「영노과장(営奴/ヨンノ科場)、第3幕 「할미영감과장(ハルミ・ヨンガン科場)」、第4幕 「사자무광장(獅子舞/サジャム科場)」 から成る。今回の企画公演では、本来は1匹しか出てこない獅子が5匹登場するとのこと。
第1幕 「양반과장(両班/ヤンバン科場)」 に登場する5人の양반(両班=ヤンバン)(▼)。高麗・李朝時代の特権的な身分階層だ。

ヤンバンに仕える下男・말뚝이(マルトゥギ)(▼)。話の中では、自分が仕えるヤンバンのことを辛辣に風刺する。

マルトゥギの後ろに見えているのは、第2幕 「영노과장(営奴/ヨンノ科場)」 に登場するヨンノ(▼)。

ヨンノに続いて、第3幕 「할미영감과장(ハルミ・ヨンガン科場)」 に登場するハルミ・ヨンガン・妾の제대각시(チェデカッシ)(▼)。

つづく
영남교방청춤보존회(嶺南教坊庁舞保存会)の舞、부산농악(釜山農楽)の演奏・舞に続いて、수영야류(水営野遊=スヨンヤリュ)が披露される。
「水営野遊 保存会」 会長 김성율(金成律=キム・ソンユル)氏の、水営野遊の由来に関する説明(水営民俗保存会HPより)(▼)。
*****
口承によれば、数百年前に慶尚左道・水軍節度使営が駐屯したとき、水使が陜川(ハプチョン)草溪(チョゲ)栗旨里(パンマリ)(現、慶南 陜川郡 徳谷面 栗旨里)の竹広大牌(デグァンデペ)の五広大(オグァンデ)を招いて踊らせたことから始まったという説と、水営の人々が栗旨里で(劇を)観て始まったという説がある。その当時の水営野遊の踊り手(ノリクン)は水営地方の生え抜きで、庶民や中間階層(ヤンバンと庶民の間の階層)の中で最も歌舞に長けていた人だった。
この地域で歌舞に長けている人のほとんどは、生活に余裕があって風流を楽しみ、周囲からも認められた人物だった。水営野遊は生え抜きによる代表的な탈놀음(タルノル厶=仮面劇)だった。
들놀음(トゥルノルム=野遊び)である水営野遊は、水営地方の農耕儀礼から自生的に発生して演劇へと発達しながら、朝鮮後期に떠돌이 탈놀음(トドリ タルノルム=流れ者仮面劇)の影響を受け、現在のような劇に発展したと思われる。
特に水営は海に接しているため、漁をするときに行われる漁労謡・踊りと、農作業をするときの農謡・踊りなどがその原型となっている。
また生活と踊りは互いに影響を及ぼしていた。生活の中に踊りがあり、踊りの文化は生活文化の延長線上にあった。踊りはすなわち生活であり、生活は踊りにつながるという美的構造をもとに、水営野遊は当時の生活像を反映していた。踊りそのものが彼らの生活へと通じていた。
そのため、水営野遊の덧배기(トッベギ)踊りは、ある特定の人の専門的な踊りではなく、大衆の中に自然発生的に生じたものである。飾り気のない身体の動きがリズムに乗って踊りへと昇華された。生活と密着しながら発展していった生活舞踊といえる。
このような、本能的で人間的な純粋舞踊のスタイルが、劇としてすでに特化していた水営野遊の中に溶けこんでいった。そして 「歌・舞・戯」 という3大要素から成る美的構造を作りながら、より土俗性の濃い踊りになっていった。水営野遊は、들놀음(トゥルノルム)という韓国仮面劇のルーツとも言える。
*****
まずは、登場人物全員のパレードから。
提灯行列(▼)。昔は旧正月の月が昇る頃に行われていたため、提灯に先導されていた。
水営野遊は、第1幕 「양반과장(両班/ヤンバン科場)」、第2幕 「영노과장(営奴/ヨンノ科場)、第3幕 「할미영감과장(ハルミ・ヨンガン科場)」、第4幕 「사자무광장(獅子舞/サジャム科場)」 から成る。今回の企画公演では、本来は1匹しか出てこない獅子が5匹登場するとのこと。
第1幕 「양반과장(両班/ヤンバン科場)」 に登場する5人の양반(両班=ヤンバン)(▼)。高麗・李朝時代の特権的な身分階層だ。
ヤンバンに仕える下男・말뚝이(マルトゥギ)(▼)。話の中では、自分が仕えるヤンバンのことを辛辣に風刺する。
マルトゥギの後ろに見えているのは、第2幕 「영노과장(営奴/ヨンノ科場)」 に登場するヨンノ(▼)。
ヨンノに続いて、第3幕 「할미영감과장(ハルミ・ヨンガン科場)」 に登場するハルミ・ヨンガン・妾の제대각시(チェデカッシ)(▼)。
つづく
Posted by dilbelau at 20:48│Comments(0)
│文化・芸術・エンタメ