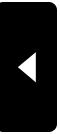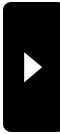2012年04月13日
水営城の南門 3
つづき
囲碁に興ずるおじさんたちのすぐそばには、碑石がずらりと並んでいる。

そばの案内文によると、
ここは慶尚左道水軍節度使営の跡地です。
左水営の総司令官である水軍節度使は、正3品の武官で通称 「水使」 といい、洛東江の東から慶州にいたる地域の海岸を守る任務を遂行しました。
ここにある33の碑石は、朝鮮時代の仁祖17(1639)年から高宗27(1890)年までの水軍節度使と副官である虞候の、在任中の功徳を称えるために建てられた善政碑で、左水営城址の整備・復元事業の一環として水営城の南門の周辺に散らばっていたものをここに集め、在任年度順に新しく整備しました。
とのこと。上記、水営城の南門というのがこちら(▼)。有形文化財第17号に指定されている。

東南海岸の防御の役割を担った水軍の本営の 「慶尚左道水軍節度使営」 は 「慶尚左水営」 と略して呼ばれていた。この門は、慶尚左水営の南門である。アーチの形をしており、前面の柱には一対の狛犬の彫刻が配置されている。これは倭寇の動きを監視するというこの城の性格を象徴しているのだそう。
この南門はもともとここ(公園内▲)にあったのではない。水営史蹟公園前の道路脇に 「南門の跡」 という表示がある(▼)。

案内文によると、
ここは朝鮮時代の慶尚左道の水軍節度使営城の南門のあった場所である(左水営城または水営城と呼ぶ)。もともと水営城は、蔚山の開雲浦に設置されていたが、後にここへ移築された。
その後、1635年に釜山の戡蠻夷浦へ移されたが、1652年に再び現在のこの地に移されてきた(蔚山の開雲浦→釜山の水営→釜山の戡蠻夷浦→釜山の水営)。
現在残っている水営城の南門は1692年に造られたものであるが、特に南門前後の虹霓と虹霓基石の原型がよく保存されている。この城門は水営初等学校の校門として使われていたが、現在は水営公園の中に移されている。
現在の南門から水営史蹟公園内に入ったところには、「水営姑堂」 という小さなお堂がある(▼)。

案内文によると、
水営姑堂では朝鮮時代、水使が 「国泰民安」 を司る纛神の祭祀を行い、以降、水営城民が村の平和と豊穣を祈る土地之神の祭祀を行ったと伝わっている。
現在の水営姑堂では、纛神とともに、植民地時代の日本軍のいじめを退けた宋氏ばあさんの気骨の精神を讃えるため、毎年旧暦の小正月、水営郷友会の主管により祭祀が行われている。水営姑堂は、またの名を宋氏ハルメ(ばあさん)堂、サンジョンモリ(山頂)ハルメ堂ともいう。
水営姑堂は、約400年前(文禄・慶長の役以前)に建てられたと推定されている。その後、祭堂が古びて倒壊したので1936年に再建した。現在の建物は1981年、愛郷人の金己培(キム・ギベ)氏により増築・修理され、2003年にはその子の金鐘秀(キム・ジョンス)氏がさらに改修した。正面から見て祭堂の右は城主神堂であり、左は纛神廟である。
とくに纛神廟には兵営の大将の前面に立てる纛旗が安置され、軍旗の神を祀っていることが一般的な祭堂とは異なる特徴を持つ。また、祭堂に隣接した天然記念物の椋の木は地神木で、黒松は軍神木として考えられ、水営の住民には子供が軍隊に入るなど遠くへ行く際に、水営姑堂や神木に無事と安寧を祈願すると効果があると信じられている。
水営姑堂のそばには、まるでお堂を守るように寄り添って巨木が立っている(▼)。天然記念物270号に指定されている黒松(海松)で、樹齢は400年以上と言われている。

水営城があった当時、軍船や兵士を保護する神聖な木と考えられていたそうだ。

また、水営史蹟公園の道路に面した側には、安龍福将軍の祠堂と銅像がある(▼)。案内文によると、安龍福は朝鮮時代の東莱出身の水軍であり、鬱陵島と独島の守護に多大な貢献をしたことで、周りの人々から将軍と讃えられたそうだ。
安龍福将軍の業績を末永く讃えるため、2001年3月26日、水営区民に呼びかけ、将軍を祀った祠堂と銅像を建て、1967年に造られ水営公園の頂上にあった忠魂塔を移し、新しくしたそうだ。


つづく
囲碁に興ずるおじさんたちのすぐそばには、碑石がずらりと並んでいる。
そばの案内文によると、
*****
ここは慶尚左道水軍節度使営の跡地です。
左水営の総司令官である水軍節度使は、正3品の武官で通称 「水使」 といい、洛東江の東から慶州にいたる地域の海岸を守る任務を遂行しました。
ここにある33の碑石は、朝鮮時代の仁祖17(1639)年から高宗27(1890)年までの水軍節度使と副官である虞候の、在任中の功徳を称えるために建てられた善政碑で、左水営城址の整備・復元事業の一環として水営城の南門の周辺に散らばっていたものをここに集め、在任年度順に新しく整備しました。
*****
とのこと。上記、水営城の南門というのがこちら(▼)。有形文化財第17号に指定されている。
東南海岸の防御の役割を担った水軍の本営の 「慶尚左道水軍節度使営」 は 「慶尚左水営」 と略して呼ばれていた。この門は、慶尚左水営の南門である。アーチの形をしており、前面の柱には一対の狛犬の彫刻が配置されている。これは倭寇の動きを監視するというこの城の性格を象徴しているのだそう。
この南門はもともとここ(公園内▲)にあったのではない。水営史蹟公園前の道路脇に 「南門の跡」 という表示がある(▼)。
案内文によると、
*****
ここは朝鮮時代の慶尚左道の水軍節度使営城の南門のあった場所である(左水営城または水営城と呼ぶ)。もともと水営城は、蔚山の開雲浦に設置されていたが、後にここへ移築された。
その後、1635年に釜山の戡蠻夷浦へ移されたが、1652年に再び現在のこの地に移されてきた(蔚山の開雲浦→釜山の水営→釜山の戡蠻夷浦→釜山の水営)。
現在残っている水営城の南門は1692年に造られたものであるが、特に南門前後の虹霓と虹霓基石の原型がよく保存されている。この城門は水営初等学校の校門として使われていたが、現在は水営公園の中に移されている。
*****
現在の南門から水営史蹟公園内に入ったところには、「水営姑堂」 という小さなお堂がある(▼)。
案内文によると、
*****
水営姑堂では朝鮮時代、水使が 「国泰民安」 を司る纛神の祭祀を行い、以降、水営城民が村の平和と豊穣を祈る土地之神の祭祀を行ったと伝わっている。
現在の水営姑堂では、纛神とともに、植民地時代の日本軍のいじめを退けた宋氏ばあさんの気骨の精神を讃えるため、毎年旧暦の小正月、水営郷友会の主管により祭祀が行われている。水営姑堂は、またの名を宋氏ハルメ(ばあさん)堂、サンジョンモリ(山頂)ハルメ堂ともいう。
水営姑堂は、約400年前(文禄・慶長の役以前)に建てられたと推定されている。その後、祭堂が古びて倒壊したので1936年に再建した。現在の建物は1981年、愛郷人の金己培(キム・ギベ)氏により増築・修理され、2003年にはその子の金鐘秀(キム・ジョンス)氏がさらに改修した。正面から見て祭堂の右は城主神堂であり、左は纛神廟である。
とくに纛神廟には兵営の大将の前面に立てる纛旗が安置され、軍旗の神を祀っていることが一般的な祭堂とは異なる特徴を持つ。また、祭堂に隣接した天然記念物の椋の木は地神木で、黒松は軍神木として考えられ、水営の住民には子供が軍隊に入るなど遠くへ行く際に、水営姑堂や神木に無事と安寧を祈願すると効果があると信じられている。
*****
水営姑堂のそばには、まるでお堂を守るように寄り添って巨木が立っている(▼)。天然記念物270号に指定されている黒松(海松)で、樹齢は400年以上と言われている。
水営城があった当時、軍船や兵士を保護する神聖な木と考えられていたそうだ。
また、水営史蹟公園の道路に面した側には、安龍福将軍の祠堂と銅像がある(▼)。案内文によると、安龍福は朝鮮時代の東莱出身の水軍であり、鬱陵島と独島の守護に多大な貢献をしたことで、周りの人々から将軍と讃えられたそうだ。
安龍福将軍の業績を末永く讃えるため、2001年3月26日、水営区民に呼びかけ、将軍を祀った祠堂と銅像を建て、1967年に造られ水営公園の頂上にあった忠魂塔を移し、新しくしたそうだ。
つづく
Posted by dilbelau at 09:02│Comments(0)
│文化・芸術・エンタメ