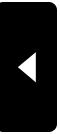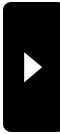2012年03月23日
美術品になった魚の木箱
ドンドンドン! ダンダンダンダン! まるで木工所に来たようだ。スタッフも忙しそうに動いている。展示場は数多くの木箱でいっぱいだ。特有の木の香りが鼻をくすぐる。展示場1階の入り口にはアーチ形のトンネルが、中に入るとまた別の形の木箱のオブジェが。倉庫のようでもあり、部屋のようでもある。

3月14日午後、釜山市中区中央洞の「ギャラリー604」。パリと東京を行き来しながら、精力的にインスタレーション(設置美術)活動を行っている川俣正さん(59)の個人展(3月17日~5月5日)を前に、仕上げの作業の真っ最中だった。彼は現在、パリの「エコール・ド・フランス」の教授でもある。彼は1982年、28歳という若さでベニス・ビエンナーレの日本館作家として招請された有名な作家だ。ペインティング作品が優勢だった80年代はじめ、物を積んでオブジェを作る破格の作品で注目を集めた。今は美術界だけでなく、建築界でもかなり知られている。
今回の展示でもやはり、木を積み上げたオブジェを展示する。しかし、木といっても平凡な木ではない。市場でよく見かける魚を入れる木箱だ。使われた木箱は実に3,600個。川俣さんはなぜ、あえて魚を入れる木箱を作品材料に選んだのだろう。「2年前釜山に来たときに思いついた構想なんです。釜山を代表するチャガルチ市場で偶然、魚を入れる木箱が山のように積まれている様子を見て、ピンと来たんです」。彼はその魚の木箱を、一番釜山らしい材料だと感じたのだそう。はじめは魚の入っていた木箱をそのまま使おうと考えた。しかし生臭いためあきらめ、1個あたり1,500ウォンで新品を注文して作業することにしたのだと。
展示場の地下1階には、木でできた巨大な滝が展示されている。木箱がこれでもかというほど積み上げられ、まるで箱の山のようだが、実は彼の精巧な構想から誕生した作品だ。見た目はすぐにでも崩れてきそうだが、針金より太いケーブル線で枠を作り、その上に木箱を重ねて置いたり、針金で箱同士をつなげてあるので、崩れる心配はない。オブジェの内側には空間があって、多少暗いが、木箱の隙間から差し込む光が見る人を幻想的な気分にさせる。子供のころかくれんぼをして遊んだときの感じを思い出す。
3月11日に釜山に来た川俣さんは、スタッフ5~6人と一緒に作品を作っていた。その設置作業は特に美術専門家でなくても、特別な技術を持たない一般人でも参加することができる。今まで彼は、ほとんどの作業過程で地元の人を使ってきた。「地元の人が参加し、地域の象徴物を利用して何かを作りだすということは、私の設置作品のもう1つの意味でもある」と彼は説明する。「地域の象徴的な材料を利用して、こんなふうに作品を作ることもできるんだということをお見せするんですよ。観客がじかに体験できるように」。
2階の展示場では以前、アメリカのマイアミ州やフランス、日本など世界各国で開かれたプロジェクトの模型を見ることができる。また今回の設置作業の過程を記録した映像も上映される。
一方彼は3月20日に東京で、津波の犠牲者の追悼1周年という意味を込めた大型プロジェクト(橋に設置したテラス)も公開する予定だ。

ギャラリー604
釜山市中区大庁路138番キル3
(051) 245-5259
開館時間:10:00~18:30
休館日:日曜日
3月14日午後、釜山市中区中央洞の「ギャラリー604」。パリと東京を行き来しながら、精力的にインスタレーション(設置美術)活動を行っている川俣正さん(59)の個人展(3月17日~5月5日)を前に、仕上げの作業の真っ最中だった。彼は現在、パリの「エコール・ド・フランス」の教授でもある。彼は1982年、28歳という若さでベニス・ビエンナーレの日本館作家として招請された有名な作家だ。ペインティング作品が優勢だった80年代はじめ、物を積んでオブジェを作る破格の作品で注目を集めた。今は美術界だけでなく、建築界でもかなり知られている。
今回の展示でもやはり、木を積み上げたオブジェを展示する。しかし、木といっても平凡な木ではない。市場でよく見かける魚を入れる木箱だ。使われた木箱は実に3,600個。川俣さんはなぜ、あえて魚を入れる木箱を作品材料に選んだのだろう。「2年前釜山に来たときに思いついた構想なんです。釜山を代表するチャガルチ市場で偶然、魚を入れる木箱が山のように積まれている様子を見て、ピンと来たんです」。彼はその魚の木箱を、一番釜山らしい材料だと感じたのだそう。はじめは魚の入っていた木箱をそのまま使おうと考えた。しかし生臭いためあきらめ、1個あたり1,500ウォンで新品を注文して作業することにしたのだと。
展示場の地下1階には、木でできた巨大な滝が展示されている。木箱がこれでもかというほど積み上げられ、まるで箱の山のようだが、実は彼の精巧な構想から誕生した作品だ。見た目はすぐにでも崩れてきそうだが、針金より太いケーブル線で枠を作り、その上に木箱を重ねて置いたり、針金で箱同士をつなげてあるので、崩れる心配はない。オブジェの内側には空間があって、多少暗いが、木箱の隙間から差し込む光が見る人を幻想的な気分にさせる。子供のころかくれんぼをして遊んだときの感じを思い出す。
3月11日に釜山に来た川俣さんは、スタッフ5~6人と一緒に作品を作っていた。その設置作業は特に美術専門家でなくても、特別な技術を持たない一般人でも参加することができる。今まで彼は、ほとんどの作業過程で地元の人を使ってきた。「地元の人が参加し、地域の象徴物を利用して何かを作りだすということは、私の設置作品のもう1つの意味でもある」と彼は説明する。「地域の象徴的な材料を利用して、こんなふうに作品を作ることもできるんだということをお見せするんですよ。観客がじかに体験できるように」。
2階の展示場では以前、アメリカのマイアミ州やフランス、日本など世界各国で開かれたプロジェクトの模型を見ることができる。また今回の設置作業の過程を記録した映像も上映される。
一方彼は3月20日に東京で、津波の犠牲者の追悼1周年という意味を込めた大型プロジェクト(橋に設置したテラス)も公開する予定だ。
*釜山日報3月16日2面より

ギャラリー604
釜山市中区大庁路138番キル3
(051) 245-5259
開館時間:10:00~18:30
休館日:日曜日
Posted by dilbelau at 08:57│Comments(0)
│文化・芸術・エンタメ