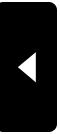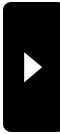2010年04月23日
'10.4.23(金)必見!藤本巧氏写真展
つづき
どれも白黒写真で、人物や風景を対象にしたもの。主に1970~1980年代の作品で、中には1969年の作品というものもあり、最近の韓国しか知らない私にとっては、どれもこれも魅力的でひきつけられるような作品ばかりだ。
中でも私が一番気に入ったのは、こちらの写真。

写真展のポスターにも使われているこの写真、後で直接藤本氏にうかがったところ、2人のおばさんは口げんかをしているのだそうだ。首の筋を立て、口を尖らせ目を見開いて、大きな声で何かを主張しているらしいおばさんの様子は、じっと見ているとまるでその声まで聞こえてきそうなぐらい、表情豊かで迫力がある。

展示されているほかの作品も、人物はどれも生き生きと表情豊かで、また風景はその場の空気を感じられるほどに臨場感にあふれている。特にチャガルチは、今でも活気とエネルギーに満ち溢れてるように感じるが、藤本氏の写真に写し出されている当時の様子は、今以上の迫力・人の生きる力を感じる。
人物も風景も、自然の営みの中のある一瞬を見事に切り取った、その時、その場の息遣いを感じられるような見事な作品ばかりだ。
こちらは藤本氏が韓国を初めて訪れたときに撮った写真の1枚だそうで、통도사(通度寺)の米蔵へ上がる木製の梯子。

会場内で販売されていた 『STESSA 一人ひとりの韓・日・交・流・誌 vol.8 2010』 の中にもこの写真は大きく紹介されていた。写真に添えられた文章がとても印象的だった。
「君は知らぬまに、人の心にスッと入り込む特技がある」 とある作家に言われたことがあった。はじめて司馬遼太郎邸にお伺いしたのは、私が二十四歳のときだった。それ以前、私は柳宋悦の思想に傾倒していた。李朝の世界に憧れて、なんども韓国の朽ちた寺院や、この国の原風景が漂う農村を訪ねては写真を撮っていた。その当時の韓国は戒厳令下であった。今日とは違って日本人の渡韓者はとても珍しかった。(『風韻』 あとがき)
つづく
どれも白黒写真で、人物や風景を対象にしたもの。主に1970~1980年代の作品で、中には1969年の作品というものもあり、最近の韓国しか知らない私にとっては、どれもこれも魅力的でひきつけられるような作品ばかりだ。
中でも私が一番気に入ったのは、こちらの写真。
写真展のポスターにも使われているこの写真、後で直接藤本氏にうかがったところ、2人のおばさんは口げんかをしているのだそうだ。首の筋を立て、口を尖らせ目を見開いて、大きな声で何かを主張しているらしいおばさんの様子は、じっと見ているとまるでその声まで聞こえてきそうなぐらい、表情豊かで迫力がある。
展示されているほかの作品も、人物はどれも生き生きと表情豊かで、また風景はその場の空気を感じられるほどに臨場感にあふれている。特にチャガルチは、今でも活気とエネルギーに満ち溢れてるように感じるが、藤本氏の写真に写し出されている当時の様子は、今以上の迫力・人の生きる力を感じる。
人物も風景も、自然の営みの中のある一瞬を見事に切り取った、その時、その場の息遣いを感じられるような見事な作品ばかりだ。
こちらは藤本氏が韓国を初めて訪れたときに撮った写真の1枚だそうで、통도사(通度寺)の米蔵へ上がる木製の梯子。
会場内で販売されていた 『STESSA 一人ひとりの韓・日・交・流・誌 vol.8 2010』 の中にもこの写真は大きく紹介されていた。写真に添えられた文章がとても印象的だった。
*****
「君は知らぬまに、人の心にスッと入り込む特技がある」 とある作家に言われたことがあった。はじめて司馬遼太郎邸にお伺いしたのは、私が二十四歳のときだった。それ以前、私は柳宋悦の思想に傾倒していた。李朝の世界に憧れて、なんども韓国の朽ちた寺院や、この国の原風景が漂う農村を訪ねては写真を撮っていた。その当時の韓国は戒厳令下であった。今日とは違って日本人の渡韓者はとても珍しかった。(『風韻』 あとがき)
*****
(『風韻』 は、2005年フィルムアート社から出版された、鶴見俊輔氏との共著。)つづく
Posted by dilbelau at 15:07│Comments(0)
│文化・芸術・エンタメ