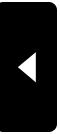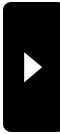2010年03月24日
'10.3.24(水)韓紙工芸作り・ついに完成!! 3
つづき
さて、周囲の4辺を上面・下面ともに貼り終えたら、中央に図柄を貼る作業。トレイの裏面の部分は、先に貼ってしまうとべたついてその後の作業がやりにくくなるので、最後に回すのだそうだ。
この図柄を貼る作業がまた一段と神経を使う・・・。
色の韓紙は貼る位置が多少ずれても修正しやすいが、図柄は辺縁が細かく複雑に入り組んでいるので、一旦貼ってしまうとはがすことはできない(図柄が破れてしまう)。そのため、図柄を貼る位置を上下左右のバランスを見ながら決め、位置が決まったら左半分を手で押さえておきながらまずは右半分を貼り、続いて残りの左半分を貼る、といった具合に慎重に貼っていく。

貼れた~!!
そして最後に、トレイの裏面も同様に空気が入らないように、ヘラを使って丁寧に貼る。
以上で、貼る作業は終了!
次に仕上げの作業に入る。
ここからは鄭さんが熟練の技を見せてくださる。
まずはトレイの全面に、先ほどまで使っていた鄭さんお手製の小麦粉糊を、水で薄く溶いたものをムラなく刷毛で塗っていく。上面を塗ったらドライヤーで乾かして、下面も塗って乾かす。この作業を2~3回繰り返すのだそうだ。


この作業の後に、最後に仕上げのコーティング剤を塗るのだが、薄い小麦粉糊を塗らずに直にコーティング剤を塗ってしまうと、コーティング剤がトレイの韓紙にしみこんでしまってコーティングの役割を果たさないのだそうだ。薄い小麦粉糊は、いわばコーティング剤の下地というわけだ。
またこの薄く溶いた小麦粉糊は、1回塗るより2回、2回塗るより3回と重ね塗りしていくたびに、韓紙もがちっと固まり発色もよくなるのだが、しかし注意が必要。あまりに多く塗りすぎると、やがて乾いていく段階で小麦粉の成分が白く浮き出してしまうことがあるのだそうだ。そうなってしまうともう修復不可能なので、たくさん塗れば塗るほどいいというわけではなく、加減が必要だということだ。
さて、この日は薄い小麦粉糊を3回重ね塗りしてくださった。次にいよいよ最後の最後の仕上げ、コーティング剤だ。一般的にコーティング・つや出しといえばニスを使うことが多いが、ニスだと匂いがきつくまた乾ききるまでに時間がかかるというデメリットがある。
特に、「アルプス」 のようにレストラン内で体験教室をしている場合、ニスの匂いが店内に漂うのはご法度。また体験教室の一定の時間内で作品を仕上げるためには、ある程度速く乾くものが好ましい。ということで、鄭さんは知人を通して仕入れている水性の特殊コーティング剤を、小麦粉糊と混ぜ合わせて使われているのだそうだ。
このコーティング剤を塗るときにも、注意しなければならないことがある。
つやを出したいからと、コーティング剤をたくさん塗りすぎてしまうと、今度はコーティング剤の厚みにムラができたり、角の部分にコーティング剤がたまってしまったりしてしまう。それがそのまま固まると、見た目にも手触り的にもよくないので、これまた適量のコーティング剤をムラなく丁寧に塗っていくことが大切。
やはり塗ったらドライヤーで乾かし、再度塗っては乾かし、を繰り返す(この日は2度塗り)。ただし、コーティング剤を乾かすときは、熱風を当ててしまうとコーティング剤に気泡が生じてしまい、そうなってしまうと修復するのに大変なので、冷たい風と温かい風を交互に、トレイから少し離したところから当てるのがコツなのだそうだ。
(鄭さんが普段ご自分の作品を作られるときは、ドライヤーを使わず自然乾燥させるのだそうだ。体験教室では時間の関係もあるので便宜上。)
ついに、完成!!


紙でできているとは思えないほど、しっかりとした仕上がりに。ほどよくつやも出て美しい。家に持ち帰っても、しばらくは立てかけて乾かしておいた方がいいですよとのこと。多くの部分を鄭さんに手伝ってもらったとはいえ、やはり自分で作ったという充実感は心地よい。Kさん、気に入ってくださるだろうか。
つづく
さて、周囲の4辺を上面・下面ともに貼り終えたら、中央に図柄を貼る作業。トレイの裏面の部分は、先に貼ってしまうとべたついてその後の作業がやりにくくなるので、最後に回すのだそうだ。
この図柄を貼る作業がまた一段と神経を使う・・・。
色の韓紙は貼る位置が多少ずれても修正しやすいが、図柄は辺縁が細かく複雑に入り組んでいるので、一旦貼ってしまうとはがすことはできない(図柄が破れてしまう)。そのため、図柄を貼る位置を上下左右のバランスを見ながら決め、位置が決まったら左半分を手で押さえておきながらまずは右半分を貼り、続いて残りの左半分を貼る、といった具合に慎重に貼っていく。
貼れた~!!
そして最後に、トレイの裏面も同様に空気が入らないように、ヘラを使って丁寧に貼る。
以上で、貼る作業は終了!
次に仕上げの作業に入る。
ここからは鄭さんが熟練の技を見せてくださる。
まずはトレイの全面に、先ほどまで使っていた鄭さんお手製の小麦粉糊を、水で薄く溶いたものをムラなく刷毛で塗っていく。上面を塗ったらドライヤーで乾かして、下面も塗って乾かす。この作業を2~3回繰り返すのだそうだ。
この作業の後に、最後に仕上げのコーティング剤を塗るのだが、薄い小麦粉糊を塗らずに直にコーティング剤を塗ってしまうと、コーティング剤がトレイの韓紙にしみこんでしまってコーティングの役割を果たさないのだそうだ。薄い小麦粉糊は、いわばコーティング剤の下地というわけだ。
またこの薄く溶いた小麦粉糊は、1回塗るより2回、2回塗るより3回と重ね塗りしていくたびに、韓紙もがちっと固まり発色もよくなるのだが、しかし注意が必要。あまりに多く塗りすぎると、やがて乾いていく段階で小麦粉の成分が白く浮き出してしまうことがあるのだそうだ。そうなってしまうともう修復不可能なので、たくさん塗れば塗るほどいいというわけではなく、加減が必要だということだ。
さて、この日は薄い小麦粉糊を3回重ね塗りしてくださった。次にいよいよ最後の最後の仕上げ、コーティング剤だ。一般的にコーティング・つや出しといえばニスを使うことが多いが、ニスだと匂いがきつくまた乾ききるまでに時間がかかるというデメリットがある。
特に、「アルプス」 のようにレストラン内で体験教室をしている場合、ニスの匂いが店内に漂うのはご法度。また体験教室の一定の時間内で作品を仕上げるためには、ある程度速く乾くものが好ましい。ということで、鄭さんは知人を通して仕入れている水性の特殊コーティング剤を、小麦粉糊と混ぜ合わせて使われているのだそうだ。
このコーティング剤を塗るときにも、注意しなければならないことがある。
つやを出したいからと、コーティング剤をたくさん塗りすぎてしまうと、今度はコーティング剤の厚みにムラができたり、角の部分にコーティング剤がたまってしまったりしてしまう。それがそのまま固まると、見た目にも手触り的にもよくないので、これまた適量のコーティング剤をムラなく丁寧に塗っていくことが大切。
やはり塗ったらドライヤーで乾かし、再度塗っては乾かし、を繰り返す(この日は2度塗り)。ただし、コーティング剤を乾かすときは、熱風を当ててしまうとコーティング剤に気泡が生じてしまい、そうなってしまうと修復するのに大変なので、冷たい風と温かい風を交互に、トレイから少し離したところから当てるのがコツなのだそうだ。
(鄭さんが普段ご自分の作品を作られるときは、ドライヤーを使わず自然乾燥させるのだそうだ。体験教室では時間の関係もあるので便宜上。)
ついに、完成!!
紙でできているとは思えないほど、しっかりとした仕上がりに。ほどよくつやも出て美しい。家に持ち帰っても、しばらくは立てかけて乾かしておいた方がいいですよとのこと。多くの部分を鄭さんに手伝ってもらったとはいえ、やはり自分で作ったという充実感は心地よい。Kさん、気に入ってくださるだろうか。
つづく
Posted by dilbelau at 16:28│Comments(0)
│韓国料理・文化体験