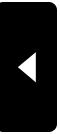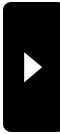2012年02月19日
海の恵みがずらりと 9
つづき
大辺港あたりの様子を、再び神谷丹路氏の 『韓国歴史漫歩』(明石書店・2003年)の中からご紹介。
この港町大辺生まれの鄭石奉(チョン・ソクボン)さん(67歳)が、大辺港周辺の昔の様子を語ってくださった。
「日帝時代の初期は、大辺のほうが、機張よりも大きな町だったそうですよ。郵便局もあったし、日本人小学校もあったし、駐在所もあって。駐在所はもちろん日本人を保護するためにあったんですけどね。それから遊郭もありましたよ。漁師相手のね。海雲台から大辺に直接来るバスの便もあって、あの頃のほうが今より便利がよかったくらいです。ところがいつの頃からか、大辺よりも機張のほうが発展しはじめて、しだいに大辺は田舎の港町になってしまったそうです」
船大工のワタナベ、商店をやっていたイナナカ、ニシヤマ・・・かつてこの町に住んだ日本人の名を、おぼろげな記憶をたどりながら教えてくださった。初め季節ごとに通漁していた漁民たちが、そのうち定住するようになった。これがまさに 「植民」 であり、「侵略」 の実相でもある。遊郭もあったとなれば、かなり景気もよかったのだろう。今の漁村の慎ましやかな佇まいからは想像もつかないが、100年前の大きな勢いに乗った漁民たちの暮らしぶりに思いをはせてみる。
『朝鮮総督府統計年報』 によれば、岡山県が1912(大正1)年大辺を漁業根拠地にする出漁団日比組の団員90に対し300円を、1915(大正4)年には団員30に対し400円を下付している。サワラ漁を目的にこの地に出漁し、やがて 「移住」 した彼らは、日本国家の強力な漁業資金援助をバックに朝鮮出漁を敢行した。漁民たちのあたかも自由意志によって漁業活動が展開されたようにもみえるが、実はそうした漁民たちの動きを巧みに操りながら、近代の日本は朝鮮への侵略の道をひた走ったのである。
大辺や竹城里の海辺の風景は、良くも悪しくも日本との関わり抜きには語れない。倭寇の侵入口と倭城と日本人漁民という数百年の時間を隔てた3つの分布図が、奇妙なほどほぼ重なり合うのである。
港の賑やかな通りを歩いてみる。道路の片側には店舗の建物、反対側には屋台がずらりと並ぶ。どれも、大辺特産の멸치(ミョルチ=カタクチイワシ)や機張ワカメなどの乾物、ミョルチや太刀魚の塩辛などを売る店だ。網にワカメやイカを並べて干してある様子も多く見かけた。



チャガルチを思い出す風景だが、チャガルチよりは随分おとなしめの印象を受ける。呼び込みが控え目だからだろう。屋台などの前を通りかかると一応 「買ってってねー」 などと声はかかるが、声も小さめでしつこく呼びかけるわけではない。
ものすごい数のミョルチ(?)(▼)。


スルメや、いろいろな大きさの干したミョルチ、干しエビなど(▼)。

つづく
大辺港あたりの様子を、再び神谷丹路氏の 『韓国歴史漫歩』(明石書店・2003年)の中からご紹介。
*****
この港町大辺生まれの鄭石奉(チョン・ソクボン)さん(67歳)が、大辺港周辺の昔の様子を語ってくださった。
「日帝時代の初期は、大辺のほうが、機張よりも大きな町だったそうですよ。郵便局もあったし、日本人小学校もあったし、駐在所もあって。駐在所はもちろん日本人を保護するためにあったんですけどね。それから遊郭もありましたよ。漁師相手のね。海雲台から大辺に直接来るバスの便もあって、あの頃のほうが今より便利がよかったくらいです。ところがいつの頃からか、大辺よりも機張のほうが発展しはじめて、しだいに大辺は田舎の港町になってしまったそうです」
船大工のワタナベ、商店をやっていたイナナカ、ニシヤマ・・・かつてこの町に住んだ日本人の名を、おぼろげな記憶をたどりながら教えてくださった。初め季節ごとに通漁していた漁民たちが、そのうち定住するようになった。これがまさに 「植民」 であり、「侵略」 の実相でもある。遊郭もあったとなれば、かなり景気もよかったのだろう。今の漁村の慎ましやかな佇まいからは想像もつかないが、100年前の大きな勢いに乗った漁民たちの暮らしぶりに思いをはせてみる。
『朝鮮総督府統計年報』 によれば、岡山県が1912(大正1)年大辺を漁業根拠地にする出漁団日比組の団員90に対し300円を、1915(大正4)年には団員30に対し400円を下付している。サワラ漁を目的にこの地に出漁し、やがて 「移住」 した彼らは、日本国家の強力な漁業資金援助をバックに朝鮮出漁を敢行した。漁民たちのあたかも自由意志によって漁業活動が展開されたようにもみえるが、実はそうした漁民たちの動きを巧みに操りながら、近代の日本は朝鮮への侵略の道をひた走ったのである。
大辺や竹城里の海辺の風景は、良くも悪しくも日本との関わり抜きには語れない。倭寇の侵入口と倭城と日本人漁民という数百年の時間を隔てた3つの分布図が、奇妙なほどほぼ重なり合うのである。
*****
港の賑やかな通りを歩いてみる。道路の片側には店舗の建物、反対側には屋台がずらりと並ぶ。どれも、大辺特産の멸치(ミョルチ=カタクチイワシ)や機張ワカメなどの乾物、ミョルチや太刀魚の塩辛などを売る店だ。網にワカメやイカを並べて干してある様子も多く見かけた。
チャガルチを思い出す風景だが、チャガルチよりは随分おとなしめの印象を受ける。呼び込みが控え目だからだろう。屋台などの前を通りかかると一応 「買ってってねー」 などと声はかかるが、声も小さめでしつこく呼びかけるわけではない。
ものすごい数のミョルチ(?)(▼)。
スルメや、いろいろな大きさの干したミョルチ、干しエビなど(▼)。
つづく
Posted by dilbelau at 21:09│Comments(0)
│機張・日光・大辺