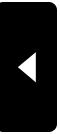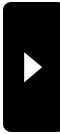2008年10月07日
2008年10月7日(火)梵魚寺(ポモサ)
おいしい東莱パジョンをいただいて、「東莱」駅から再び地下鉄に乗り「梵魚寺」駅へ。「梵魚寺」駅から梵魚寺までタクシーを利用したのだが、途中、道端に立っている女性を見かけ運転手が車をとめる。同じ梵魚寺に行くとのことで、相乗りさせてもいいかと私たちに尋ねる。韓国では「相乗り」はよくあることだと聞いていたが、私には初めての体験。
女性が乗ってからいくらもたたないうちに梵魚寺の入口へ到着。女性はまだ先まで行くとのことで、私たちだけ先に降りる。こういう場合、料金はどうなるのだろうと思ったら、運転手はその時点までの料金は私たちが払うようにと。そこから先の料金だけ、相乗りしてきた女性が払うらしい。こういう場合の料金も、払い方も運転手によっていろいろらしい。

禅寺の総本山である梵魚寺は、新羅時代の678年に高僧により創建された。16世紀末の文禄・慶長の役で焼失、本殿である大雄殿は1614年に再建され、その後1713年に補修されたそうだ。

入口の一柱門は1614年に建てられたもので、太い石柱が横一列で屋根を支える独特の様式で知られる。

梵魚寺を取り巻く山々の緑の中には、わずかに色づいている部分も。
紅葉シーズンには多くの人が訪れるそうだ。
階段を上った「天王門」とその内部。(四天王)



「天王門」の足元には、石のカエルが。

さらに奥に進んでいくと、土と瓦で作られた雰囲気のいい壁と竹。


梵魚寺の名前の由来は、

という由来の通り、魚をモチーフにした風鈴のようなものをあちこちで見かけた。




土と瓦で作られた壁。
秋を感じさせるひんやりとした澄んだ空気。



梵魚寺は、お寺での生活を体験できる「テンプルステイ」という制度のあるお寺の一つ。
韓国滞在中に、どこかのお寺で「テンプルステイ」も体験してみたいと思う。
先ほどの、土と瓦で作られた壁にはさまれた小道をずっと歩いて門を出ると、無数の岩石がゴロゴロしているところに出る。ここから3キロ半ほど遊歩道が整備されてあり、梵魚寺の庵にも行くことができる。
苔むした大きな岩石と、木々の緑、カサカサした落ち葉などが何ともいえぬ対比をなしていて美しかった。


下山するに従って、岩石の間に川の流れが。
岩に腰掛けて休んでいる人の姿も見えた。

岩の中には、人の名前らしき文字が彫られたものもいくつかあった。
帰りは市内バスに乗って、地下鉄「梵魚寺」駅まで。
街の喧騒や、派手な飲食店の看板や音楽から離れ、しばし静かなゆったりした空気を楽しむことができた。
女性が乗ってからいくらもたたないうちに梵魚寺の入口へ到着。女性はまだ先まで行くとのことで、私たちだけ先に降りる。こういう場合、料金はどうなるのだろうと思ったら、運転手はその時点までの料金は私たちが払うようにと。そこから先の料金だけ、相乗りしてきた女性が払うらしい。こういう場合の料金も、払い方も運転手によっていろいろらしい。
禅寺の総本山である梵魚寺は、新羅時代の678年に高僧により創建された。16世紀末の文禄・慶長の役で焼失、本殿である大雄殿は1614年に再建され、その後1713年に補修されたそうだ。
入口の一柱門は1614年に建てられたもので、太い石柱が横一列で屋根を支える独特の様式で知られる。
梵魚寺を取り巻く山々の緑の中には、わずかに色づいている部分も。
紅葉シーズンには多くの人が訪れるそうだ。
階段を上った「天王門」とその内部。(四天王)
「天王門」の足元には、石のカエルが。
さらに奥に進んでいくと、土と瓦で作られた雰囲気のいい壁と竹。
梵魚寺の名前の由来は、
その由来が記された「東国輿地勝覧」によると、金井山の端にとても大きい石があり、その石の上には井戸があったんだそうです。その井戸は、とても大きくいつも水で満たされている上、その光は黄金色だったんだとか。一匹の魚が五色雲に乗って空から降りてきて、その井戸で遊んだことから、空の国の魚という意味を込めて、梵魚寺という寺名になったと書かれています。(プサンナビより抜粋)
という由来の通り、魚をモチーフにした風鈴のようなものをあちこちで見かけた。
鐘楼。
本殿(大雄殿)。
土と瓦で作られた壁。
秋を感じさせるひんやりとした澄んだ空気。
梵魚寺は、お寺での生活を体験できる「テンプルステイ」という制度のあるお寺の一つ。
韓国滞在中に、どこかのお寺で「テンプルステイ」も体験してみたいと思う。
先ほどの、土と瓦で作られた壁にはさまれた小道をずっと歩いて門を出ると、無数の岩石がゴロゴロしているところに出る。ここから3キロ半ほど遊歩道が整備されてあり、梵魚寺の庵にも行くことができる。
苔むした大きな岩石と、木々の緑、カサカサした落ち葉などが何ともいえぬ対比をなしていて美しかった。
下山するに従って、岩石の間に川の流れが。
岩に腰掛けて休んでいる人の姿も見えた。
岩の中には、人の名前らしき文字が彫られたものもいくつかあった。
帰りは市内バスに乗って、地下鉄「梵魚寺」駅まで。
街の喧騒や、派手な飲食店の看板や音楽から離れ、しばし静かなゆったりした空気を楽しむことができた。
Posted by dilbelau at 23:03│Comments(0)
│梵魚寺